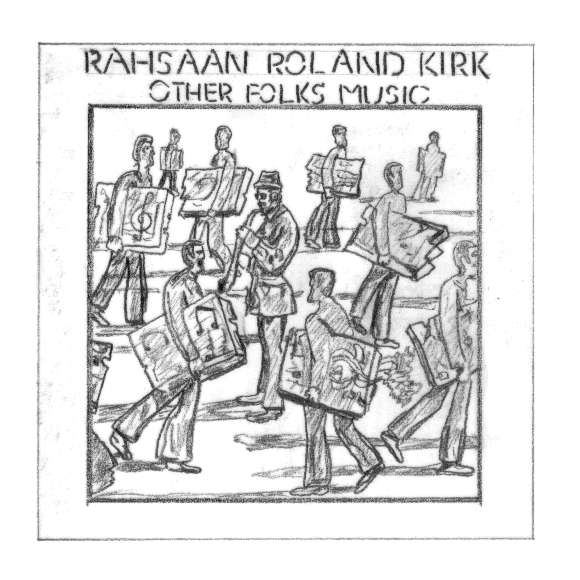
僕の夏はまだ終わっていません。 何の話かと言うと、毎年9月の頭に電験3種の試験を受けて、ぜんぜん分からなくて、 「夏の奇跡」 に期待してとりあえずマークシートを塗るだけ塗って、で、答え合わせの結果、適当に答えた奴の正答率が5択問題なのに20%以下であることに絶望して、まともに答えられた奴など端から15%くらいしかないので話にもならなくて、僕の夏が終わりました。 そういう結果に終わるのが、ここ5〜6年の恒例行事みたいになっておりました。 そんなことではいけないっ! そう一念発起した僕は、ホッケの干物とホッキ貝を買おうと決意した次第でありますが、よく考えたら魚貝類の類はあまり好きではなかったりするので、やっぱり買うのはやめる事にして。 …と、ここまでが毎年のお約束だったんですが、今年の僕は違います。 ハマグリの稚貝とアサリの稚貝くらい、違います。 僕は貝類の類があまり好きでないだけでなく、ぜんぜん詳しくもないので、もしかしたら稚貝の違いは分からなかったりするかも知れませんが、去年の僕と今年の僕との違いは僕にも分かります。 去年までの僕には、ちょっと頑張って勉強しようという気持ちがそれなりにあったんですよね。 ま、 「それなり」 にしかなかったので、結局は 「おざなり」 に終わってしまったんですが、今年の僕は 「おざなり」 なヤル気すら、まったく沸いて来なかったりします。 「おさわり」 だったら、ちょっと頑張ってみようかという気になれるんですけどねぇ。
ヤル気がないならやるだけ無駄だし、というか、ヤル気がないからやらないし、どうせやらないなら、最初からやめてやるぅ! …というので、今年は願書の提出を自粛することにしました。 毎年、頼んでもいないのに、向こうのほうから願書の申請書類を勝手に送りつけてくるので、惰性でなんとなく送り返していたんですが、今年は無視することにしました。 きりがないですからね、こういうのは。 捨てる勇気はないので、こっそりと鞄の中に幽閉しておいたんですが、今、ひっぱり出して見てみたら、提出期限は6月8日までとなっておりました。 よしっ! テメェなんてもう、用無しだぁ! シュレッダーで切り刻んで、袋に詰めてゴミ箱に捨ててやるぅ! とまあそんなことで、電験から足を洗うことに成功した僕でありますが、いや、我ながら “勇気ある撤退” でありますな。 何だか凄くすっきりとした清々しい気分なんですが、ただ、世間からはどんな目で見られることになるんですかね? 何回受けても受からなくて、とうとう諦めちゃったヘタレって、超ウケるぅ♪ そんなふうに思われているのだとしたら、不本意です。 当たっているだけに、何だか悔しいです。 諦めたんじゃない! 目指す道を変えただけなんだ! そう世間にアピールするためにも何か他の資格試験を受けて、 「超ウケるぅ♪」 と馬鹿にした奴を見返してやりたい。 そんな必要性に駆られて、とまあそんなことで、受けてきました、1級土木施工管理技士。 通称 “セコカン” と呼ばれて、このギョーカイではそれなりの知名度と権威がある資格だったりします。 僕は既に電気と管工事の 2つのジャンルを制覇しているエリートだったりするんですが、これならまだ、何とかならないこともないような気がしないでもありません。 ただ、土木は今回が初挑戦なので、どんな問題が出題されるのかよく分からなくて、ちょっぴり不安だったりするんですが、土の掘り方とか、木の切り方とか、そういう勉強が必要だったりするんですかね?
で、とりあえず参考書と過去問題集を1冊ずつ買ってみたんですが、その結果、土木と言うのは “土木” というよりむしろ、 “土鉄コンクリート” であるらしい。 そんな事実が発覚したんですが、土の掘り方はあっても、木の切り方はないんですよね。 第1章の 「土木分野」 は土質調査、盛土の施工と締固め、建設発生土の利用と埋戻し、土工機械、法面排水工、各種セメントとレディーミクストコンクリート。 そういった内容となっておりました。 おお、レディーミクストコンクリート。 何だか聞いたことがありますなー。 土建屋のおっさんからレディーミクストコンクリートの配合計画書とか、そんな名前の書類を貰ったような覚えがあります。 中身を見ても何のことかよく分からないので、表紙だけ付けて、そのまま役所の担当者に提出していたんですが、その他にもコンクリート用骨材とか、配合設計と耐久性とか、コンクリートの施工と養生とか、鉄筋の加工とか。 現場監督というのは意味も分からず土建屋のおっさんの働きっぷりをボーッと眺めて、時おり、言われるままに工事黒板に施工状況を記入して写真を撮るだけの、わりと簡単なお仕事だったりするんですが、状況によっては 「よく分からんから、書いて!」 と、黒板書きの業務を丸投げしちゃったり。 時おり、施工方法について質問されたりしても、 よく分からないので、 「そうっすねぇ。」 とか、適当に返事をするしか手だてがなかったんですが、しっかり勉強してこの資格をゲットすることが出来れば、もうちょっと何とかなるような気がしないでもなくて、何だかこう、俄然とヤル気が沸いてきましたなぁ。 かなり実務に即した内容だったりするので、もしかして、これなら何とかなるかも?
そんな希望的観測は、直接基礎、既製杭、場所打ち杭、ケーソン基礎…と、話が進んでいくに従って、次第に怪しくなってきました。 杭打ちなんてそんな本格的な土木工事は20数年この仕事をやってきて、たった1回、墨俣の現場でしか経験したことがありません。 無論、書類作成から写真撮影に至るまで、業務のほうは下請のおっさんに完全丸投げだったので、未だにあれがどういう作業だったのか、まったく把握出来てなかったりします。 監督としてやった仕事と言えば、工事現場の隣の工場のオッサンに叱られて、 「すいません、すいません!」 と平謝りしたくらいですからね。 「まったく振動の出ない工法でやります。」 という話を聞いていたので、その旨を 隣の工場の社長に申し述べて承諾を得ていたんですが、いざ始まってみれば、ドシーン!ドシーン! …と結構な振動が。 「これ、ちょっとマズくね?」 と、ヒヤヒヤしていたら、案の定、工場から社長が飛び出してきて叱られちゃったんですが、何でもとっても精密な部品の加工をしているので、 「ちょっとの振動でも、困るっ!」 と。 ま、おっしゃりたいことはよく分かるんですが、そんなこと、僕に言われてもぉ。。。 不意打ちで杭打ちしたワケではなく、事前にちゃんと通告しておいたんだから、その日は臨時休業にしちゃうとか、従業員みんなで墨俣の一夜城に遊びに行くとか、工場サイドでも何か対応策はあったと思うんですよねー。 ま、いずれにしろ、杭打ちにはあまりいい印象を持っていなかったりするんですが、今後、杭打ち工事を監督する機会は無いものと思われるので、杭について分からないまま終わってしまったとしても、まったく悔いはない。 そう思って今まで生きて来たので、参考書の中での突然の再会に戸惑いを覚えてしまいましたが、で、僕の1級土木に対する “何とかなるかも知れない感” は、第2章の 「専門土木」 に入った時点で、完膚なまでに叩き潰されることになりました。 橋梁架設、プレスストレスコンクリート、河川護岸、床固工・根固工・低水路、樋門・渓流保全工、砂防えん堤、地すべり・斜面崩壊防止対策、コンクリートダム、フィルダムと基礎のグラウチング、RCD工法と拡張レヤー工法、山岳トンネルの施工、海岸堤防、浚渫工、鉄道路盤、鉄道近接・地下施工、地下構造物・薬液注入、小口径管推進工法って、そんな超管轄外のジャンル、分かるかぁぁぁぁぁぁ!!
が、よくよく試験の概要を眺めてみると、まったく希望が持てない事はないような気がしないでもありません。 どうやら 「専門土木」 の問題は選択制になっているみたいなんですよね。 すべてのジャンルに精通する必要はなく、全部で34問あるうち、好きなのを10問選んで答えればいいみたいです。フィルダムと基礎のグラウチングとか、RCD工法とか、拡張レヤー工法とか、名前すら見たことがないような奴らは、端から無視しても大丈夫。 法規、契約・設計、施工計画、工程管理、安全管理、品質管理、環境保全といった分野は電気や管工事のセコカンとも共通するものがあるし、こういうところと 「一般土木」 でしっかり点数を稼いでおけば、何とかなるかも知れません。 全部で65問あるうち、6割の39問が合格ラインみたいですからね。 「専門土木」 10問が全滅 しちゃったとしても、残りを71点ペースで乗り切れば、大丈夫…っすよね? その計算で合ってますよね? 僕は計算問題が大の苦手だったりするので、その意味では出題の8割くらいが計算問題だったりする電験なんて、端から無理だったりするんですが、土木のセコカンは計算問題がほとんど出ないので、その点でも気分が楽です。 同じマークシート方式でも、電験が5択問題なのに対して、こっちは4択なのも嬉しいところ。 それも大抵、 「次の記述のうち、適当なものをひとつ選べ」 という問題か、 「次の記述のうち、適当でないものをひとつ選べ」 というパターンの出題だったりしますからね。 選択肢の中には必ずひとつくらい、見るからに適当では無さそうな奴が混じっていたりするので、残った3つの中から適当に選んでおけば、30%くらいの確率での “まぐれ当たり” が期待出来ます。 専門知識が皆無でも、常識さえあれば何とかなりそうなサービス問題もあったりするし、何せ土建屋相手でも2人に1人は合格するレベルだし、これはもう、何とかなるような気がしないでもないし、何とかならなかったとしても、ま、その時はその時だしー。
ということで、試験当日です。 朝からけっこう雨が降っていて、ちょっと嫌な気分になりました。 去年の電験の試験の日も雨だったんですよねー。 というか、台風直撃コースだったりしました。 その時のネタが ここ にあるんですが、来年の “電験” 、もうちょっと頑張ります。 そんな決意が語られておりますな。立派な心掛けだと思います。 で、今回は風があまり強くなかったので、持っていた小さな折りたたみで何とか雨を凌ぐことが出来て、 “友愛の傘” のお世話にならずに済んだんですが、で、試験のほうはアレです。 期間限定で ここ に試験問題と回答が掲載されているので、興味のある人はチャレンジしてみて下さい。 僕も早速、答え合わせをしてみたんですが、試験問題は時間ギリギリまで粘った人しか持ち帰ることが出来なくて、僕は開始から1時間で抜け出しちゃったので、自分がどの答えを選んだのか、今ひとつ記憶が定かではなかったりします。 おまけに自分がどの問題を選んだのかすらあやふやだったりするので、正確な点数が分からなかったりするんですが、ひとつだけ反省点を挙げるとするならば、余計なことを考えなければよかった…と。 午後の問題の最初のほうで、適当と思われるものとか、適当でないと思われるものとかを適当に選んだら、 「4」 という選択肢が4つ連続になっちゃったんですよね。 それなりに自信のある回答だったんですが、同じ数字が4つも並ぶというのは確率からして絶対におかしい! そんな迷いが生じて、3つめを 「1」 に変更しちゃいました。 回答を見たら 「4」 の4並びが正解で、しまった! 余計なことを考えなければよかった! 午前の問題には 「2」 が5つも並ぶところがあったりして、人間の心理の裏をかくなんて、ズルイや!! そう思わずにはいられませんが、覚えている限りでは、わりと自信を持って回答したのに間違っていたのもあれば、適当に選んだらマグレで当たってたのもあって、トータルで言うと、うーん、まあまあ? ま、電験の時よりは遙かに手応えがあったので、駄目だったりしなければ、大丈夫なんじゃないか? そんな気がしないでもありません。 もし大丈夫だったりした場合、今度は実地の試験が待ちかまえていたりします。 実地と言っても土を掘ったり、トンネルを掘ったり、浚渫したり、小口径管を推進したりするワケではなく、普通の筆記試験なんですが、マークシートではなくて記述式だし、施工管理に関するプチ論文みたいなのを書かなければいけないし、ちょっぴりハードルが高くて、受かる気がしません。 ちなみに試験日は10月7日(日)なんですな。 よりによって、3連休のど真ん中かいっ! 何だかまったく受ける気がしなくて、むしろ、学科試験は落ちてくれてたほうが、いいかも? そんな気になったりもするんですが、ちなみに合格発表は8月15日。 受かっても嫌だし、落ちてたらやっぱり嫌だし、何だか煩悩に悩まされるお盆になりそうなんですが、落ちるにしろ、落ちないにしろ、今日の話に特にオチはなくて、おちまい♪
とまあそんなことで、今日はローランド・カークっす。 “その他の楽器編” の神髄というか、 “キング・オブ・その他の楽器” というか、そういったキャラですよね。 この人がでちゃったら、その他の楽器編は終わったも同然なんですが、ま、ビッグバンドとかヴォーカル物とかで、あと数回は引っ張る所存ではあるんですけど。 で、僕はこの人のアルバムをけっこうたくさん持っているので、しばらくネタに困ることはないんですが、積極的に取り上げたい作品となると、実はそんなに多くなかったりします。 ジャケットに本人が写っている奴は、無駄に楽器をたくさん首からぶら下げているのが通例なので、書くのが面倒で嫌だし、音楽的にも特に後期のものはジャズの範疇に収まり切れないカオス系が多くなってきて、レビューを書くのが何だか面倒。 そんな中、僕が今回チョイスしたのは 『アザー・フォークス・ミュージック』 という1枚なんですが、ジャケットがイラスト系なので、簡単そうで悪くないと思います。 録音年は1976年で、後期というより最晩年といった位置付け。 脳卒中で半身不随になっちゃった以降の演奏と思われ、かつてのような超絶技巧は期待出来なかったりするのかも知れませんが、それもまあ人生だし、とまあそんなことで、では1曲目から聞いてみることにしましょうか。
まず最初は、誰が作ったんだかよく分かんないんだけど、たぶんカークのオリジナルなんじゃないかと思われる 「ウォーター・フォー・ロブソン・アンド・ウイリアムス」 。 僕が持ってるCDはカークの後期アトランティック盤が4枚ほど箱に入ったお買い得セットみたいな奴なんですが、現物を探しても見つからなかったので、MP3に変換してあったのをパソコンで聞いてます。 その為、詳しいデータとかが手元に無いし、日本語ライナーを無断で勝手に引用してお茶を濁すという、いつものお手軽手法も使えないし、何かと不便だったりするんですが、ま、輸入盤だったような気がするので、原文ライナーを見たところで、ほとんど意味は分からなかったりするんですけど。 で、曲のほうはアレです。 いきなり変なオッサンのアジ演説みたいなのが出てきて、かなり本格的に意味不明。 “このアルバム、失敗だったか感” が半端なかったりするんですが、その後、ハープとハーモニカとヴァイオリンとが地味に絡み合う。 そんな世界が展開される羽目になります。 日本の童謡に通じる哀愁味のようなものが感じられて、悪くはないと思うんですが、決していいとは思えないし、で、最後にまたオッサンの声が登場して、おしまい。 このオッサンがおそらくロブソンかウイリアムスかのどちらかだと思うんですが、解説が無いので何を意味しているのかよく分からなくて、アルバムの出だしとしては、大失敗に終わってしまった。 そのように評価するしかありません。 今後の展開に暗雲が立ちこめる思いです。
ということで、次。 「ザッツ・オール」 。 一転して今度は歌物ナンバーっすか。 所詮はカークのやることなので、まだまだ安心するわけにはいかんのですが、聞いてみたら普通にオシャレなバラードに仕上がっておりました。 エレピの透明な音色がいかにも70年代中盤っぽい雰囲気を醸し出しているんですが、これはこれで悪くないと思います。 カーク君は最初、テナーっぽい楽器を吹いている模様ですが、エレピ・ソロの後はトランペットにチェンジ。 これがまた、モロにマイルスだったりして、なかなかウケるんですが、この人、物真似も達者だったりしますからなぁ。 で、その後、再びテナーっぽいのに持ち変えることになるんですが、下半身不随でこれだけ吹ければ、必要にして十分。 さすがに片手だけで複数の楽器を同時に演奏するのは無理みたいなんですが、こういう妙に人間臭いカークというのも、悪くないですなー。 で、以下、ピアノの本格的なソロ → マイルス風と続いて、そのままトランペットでテーマを吹いて、おっ! 最後のところで “一人で2本の楽器を吹いちゃう奏法” にも果敢にチャレンジしている模様です。 さすがにちょっと無理矢理な感はあるんですが、転んでもタダでは起きない姿勢には、敬意を抱かずにはいられません。 凄ぇぜ、カークぅ♪
ということで、続いてはチャーリー・パーカーの 「ドナ・リー」 っすか。 これまた、カークらしからぬ選曲なんですが、何というか、死期を悟って、ジャズの原点に回帰。 そういう意図があったりするのかも知れません。 …と、ここまで書いた時点で、このアルバムにはリチャード・ウィリアムスが参加しているという事実にふと気付いたりしたんですが、先ほどのマイルスっぽいトランペットはカークの持ち替えではなく、リチャ・ウィだったんでしょうな、多分。 終盤、2つの管楽器の音が聞こえるような気がしたのも、もしかして普通に2管編成だったとか? 今さら聞き直したり、書き直したりするのも面倒なので、過去は振り返らずにこのまま先に進もうと思うんですが、とまあそんなことで、 「ドナ・リー」 。 これはアレです。 フルートとミュート・トランペットという、ちょっと変わった組み合わせの2管で演奏されているんですが、カーク君が笛を吹きながら怪しげな声を出したりしてくれるので、聞いてるこっちとしては、何だかこっ恥ずかしい思いをすることになります。 演奏そのものは超アップテンポで、賑やかというか、何とも言えず猥雑な様相を呈しておりますな。 ソロ先発はウィリアムスで、これがなかなか良好な吹きっぷりだったりするんですが、バックでは色んな打楽器が連打され、探知機片手に車だん吉が 「チャンチキおけさ」 で乱痴気騒ぎ。 そんな感じになっちゃいます。 続いてカークのフルート・ソロが登場すると “乱と痴” の気はより一層激しくなって、聞いてるこっちとしては、何だかツラい気持ちになったりもします。 熱気に溢れた超アツいプレイが滾るぜぇ! …と、前向きに評価することも出来なくは無いんですが、個人的には何かちょっと、嫌です。
…と、ここまで1勝2敗。 出だし、やや不調なんですが、でも大丈夫。 ここから挽回します。 ということで4曲目。 「シモネ」 。 もしかしたら 「サイモン」 とか 「シモン」 とか読むのが正解なのかも知れませんが、 「シモネ」 だと何となく下ネタっぽくて、オッサンの受けがよさそうなので、この読み方を採用させて頂くことにしました。ググってみたら 「シモーヌ」 という説を採用している人もいるようですが、で、演奏のほうはというと、チリン、チリンという鈴の音に続いて、鶏が首を絞められたような音が飛び出して来て、ちょっとビビります。 カーくん、また変な楽器を吹いて、悦に入っているようですなぁ。 その後、テナーっぽい楽器とトランペットとの自由な絡みのパートを経て、テーマが登場することになるんですが、おお、いいぢゃん♪ どうやらこれ、フランク・フォスターのオリジナルのようなんですが、言われてみればどこかで聞いたことがあるメロディーでありますな。 基本、モーダルな新主流派系なんですが、ファンキーな哀感もあって、いかにも日本人好みの旋律で、背中に戦慄に走ります。 ソロ先発はリチャード・ウィリアムスっすな。 ミュート・プレイなんですが、マイルスっぽさは希薄で、どちらかというとウディ・ショウっしょ? そんなスタイルだったりして、傾聴に値する出来であると言っていいと思います。 で、続いて出てくるピアノのソロもいいっすな。 2曲目と違って電気っ気は希薄で、生っぽい音なんですが、ハービーっぽいスタイルだったりして、浣腸に値する出来であると言っていいと思います。 続くカークのテナーっぽい楽器のソロは、極めてコルトレーンっぽい仕上がりとなっております。 途中、「ネイチャー・ボーイ」 のテーマを引用したりして、とってもスピリチュアルで、凄ぇ! とても半身不随のオッサンが吹いているとは思えなくて、もしかしてリハビリを超頑張ったお陰で、全身が復活したんじゃないかと思えるくらいなんですが、とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。 9分を越える長尺物なんですが、まったく長さを感じさせず、最後まで息をつかせない熱演ぶりでありまして、いやあ、よかったっす。
で、次。 「アニシャ」 。 作曲者としてトゥルーディ・ピッツの名前がクレジットされています。 おお、この 和田アキ子 っすな。 このカークのアルバムにも生ピ、もしくはエレピ奏者として何曲かに参加している模様ですが、この 「兄者」 っぽい名前のオリジナルもなかなかの出来映えだったりして、この人、作曲の才能もなかなかのものであると評価してよさそうです。 後は顔さえ可愛ければ・・・。 ま、カー君は盲目なので、さほど気にはならないのかも知れませんが、で、演奏のほうはアレです。 ハープとヴァイオリンとフルートとがお洒落に絡み合う、珠玉のブルース。 そういった感じで、しみじみと心に染みます。 カーくんも、ここでそろそろ鼻歌を交えてみようか? …とか、余計なことを考えず、素直なプレイに徹していて、何より。 中間部で聞かれる、ピットたんのものと思われる生ピのソロも良好だし、で、最後はテナーっぽい楽器でテーマが演奏されて、おしまい。 で、続く 「サンバ・クワ・ムワナンケ・ムエウシ」 とかいうのはアレです。 サンバです。 ヘンリー・マタシアイス・パーソンとかいう人が作った曲のようですが、変に股下がパーというわけでもなく、普通にいい感じにラテンで、悪くないっす。 カークはフルートを吹いていて、リチャード・ウイリアムスがミュート・トランペットを吹いていて、誰かがピアノを弾いていて、その他、ベースとかドラムスとかパーカッションとかも入っているようで、適度に賑やかで、ま、無難な仕上がりであると言えるのではなかろうかと。
ということで、ラストっす。 ヒルトン・ルイーズとかいう人の作品で、 「アライバル」 っす。 オーソドックスにハード・バピッシュな作風で、時おりカークが奇声を発する以外は、極めて普通で真っ当な仕上がりとなっております。 リチャ・ウイくんはミュートを外してオープンで堂々と勝負に挑んでいるし、カークはテナーのような楽器でメインストリームなブロウを展開しているし、誰かのピアノもスインギーにいい感じだし、とまあそんなことで、最後にタイコのソロが適度にフィーチャーされて、テーマに戻って、で、エンディングがちょっぴり無駄にクドかったりもするんですが、今日のところは以上です。
【総合評価】
1勝2敗の後、2連勝して、ひとつの引き分けを挟んで、最後はきっちりと勝利を収めた。そんな仕上がりでありました。 最初はどうなることかと思ったんですが、後半で大きく盛り返したので、全体としては、よかった。 そんな気がします。 結局のところ、マルチ楽器吹きの荒技は聞けなかったような気がするんですが、半身不随 (←たぶん) ではしょうがないし、その分、全盛期よりも人間味は増大しているような気がします。 人を食ったことがないので、人間味というのがどういう味なのか、よくは分からなかったりするんですけど。 1人で2〜3本の楽器を吹けない分、相棒のリチャード・ウィリアムスが頑張ってくれているし、馴染みやすいメロディの曲も多いし、カーク入門に最適とまでは言いませんが、聞いてカークが嫌いになるような地雷ではないし、そんなにツライこともないので、それなりにオススメ♪