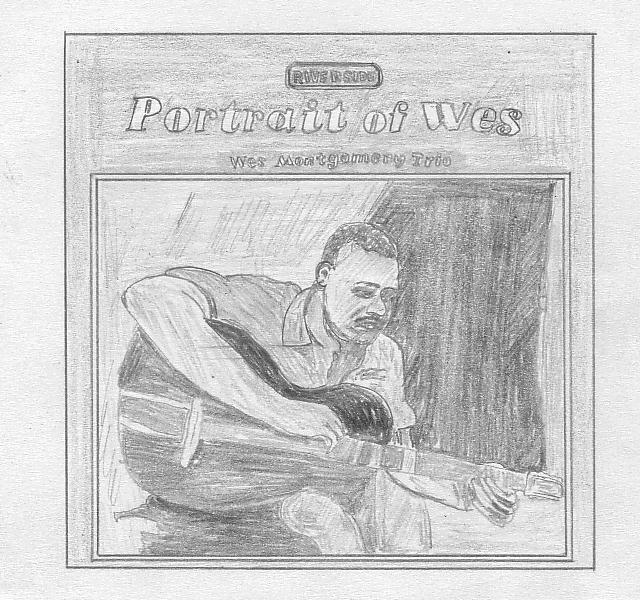
もうすぐクリスマスですね。いや、クリスマスまではまだ間があるんじゃないか?…という気もするんですが、そういう細かい話は差し置いて、クリスマスが近付くと街のあちこちからクリスマスソングが聞こえてくるようになります。よく流れてますよね、 「忍者が街にやってくる」 。…って、流れてねーよ、んなもん。 ということで、今日は “忍者” について考えてみたいと思うんですが、忍者について詳しいことは、まだ分かっておりません。唯一判明しているのは、忍者の好物はもんじゃ焼きとポークジンジャーで、健康な時は確かに忍者なんだけど、病気になって入院すると患者になっちゃう。…ということぐらいでしょうか。 肝心なことは何も分からないし、何だかとっても嘘っぽいし、忍者というのは和風のキャラだから、ポークジンジャーはやめて、豚肉の生姜焼きにしろよ!…という気がしないでもないんですが、ま、何を好んで食べようと人の勝手だとは思うんですけどね。で、忍者の概要が明らかになったところで、続いて忍者の歴史について調べてみたいと思うんですが、忍者というのはですね、 “山伏” が発展したものであると言われているようです。いや、これはちょっと意外でしたな。僕はてっきり、忍者というのは “サバ節” の流れを汲んでいるものだとばかり思っていました。が、実際にはサバ節ではなくて、山伏だったんですね。が、よくよく考えてみるとサバ節というのはダシを取るにはとっても重宝なんですが、諜報活動とかはあまり得意そうではなくて、その意味では忍者の源流としてあまり相応しくないと言えるかも知れません。
さてそこで、忍者について考える前に、簡単に山伏についても触れておきたいと思うんですが、山伏というのはアレですよね。海で修行する海伏、川で修行する川伏、ハンマーを投げるのが得意な室伏と並ぶ、 “世界四大伏(ふし)モノ” のひとつに数えられておりまして、もっぱらのところ山にこもって法螺貝を吹くという、ま、そのようなキャラでありますな。法螺貝なんか吹いて、いったい何が楽しいんだ?…という気がしないでもないんですが、ま、本人がそれで満足しているんだから他人がとやかく言う筋合いはないわけでありまして。で、その山伏が一体いつ頃、どのようにして忍者に発展していったのかと言うとですね、よくわかりません。いやあ世の中、分からないことだらけですな。ま、僕が知らないだけの話なんですけど。あまり真剣に調べる気もないしぃ。ま、細かい話はともかく、平安時代には山伏の一部が何となく忍者になったようでありまして、その個々の集団を取りまとめて伊賀忍者集団を作ったのが服部氏なんだそうであります。言わずとしれた忍者ハットリ君でありますな。ハットリ君の得意技は何といっても、サッカーで1試合に3得点以上あげること…って、そりゃ、ハットリ君やなくて、ハットトリックやがな。…と、基本的なボケをかましておいて、鎌倉時代には中国から伝わった武術が忍術に大きな影響を与えるようになって、そして甲賀の地では侍たちが忍術を学び始めるわけでありますな。えーと、甲賀、甲賀…。特に何も思いつかなかったので先に進みますが、忍者発祥の地となったのが伊賀と甲賀って、どちらも“賀”の字がつくところがとても韻を踏んでいて、いいですよね。こうなったらもう、加賀や佐賀のあたりでも忍者の養成をするとよいかも知れず、あとはえーと、羽賀研二なんかもいいかも知れませんね。誠意を持って事に当たれば、きっと立派な忍者になれるような気がします。いや、たぶん駄目なような気がしないでもないんですけど。
で、忍者が大活躍をするようになるのは何といっても戦国時代に入ってからでありまして、徳川家康や千石イエスといった人たちは数多くの忍者を抱えていたと言われております。いや、千石イエスというのはもしかしたら戦国時代の人ではなかったかも知れませんが、えーと、家康は服部半蔵を気に入り、服部半蔵の下に伊賀忍者200人を集め置き、警備をさせた。服部半蔵は出世して旗本になり、この半蔵の警備隊は江戸の伊賀組と呼ばれた。このとき半蔵が警備した江戸城の西門は半蔵門と呼ばれるようになった。…と。まるでどこかのサイトを無断で勝手に引用したような文章でありますが、なるほど、半蔵門というのはそこから来ている名前だったんですな。ひとつ賢くなりました。ということで、忍者の歴史のお話は、これでおしまいです。ずいぶんとアバウトでありましたが、“アバウト”と“山ウド”というのは、ちょっとだけ似てますね。ということで、続いて忍術や忍法について考えてみたいと思うんですが、忍者の得意技というと、まずは手裏剣を投げること、それと手裏剣を投げること、あとはえーと…、手裏剣を投げることですか。いくら考えても手裏剣を投げること以外に何も思いつきませんでしたが、忍者は手裏剣を投げるだけではなく、野球拳だって得意。…という話は聞いたことがありませんもんね。もしそういう事実があるなら、直ちに “全国野球拳大会・忍者VS女子高生” というイベントを企画・立案するところなんですが、残念ながら忍者には女子高生の服を脱がせるだけの実力はないようです。ジャンケンで負け続けて、覆面やら、忍者装束やら、パンツを脱がされるのが関の山でありましょう。たいして見たくはないですからね、忍者の局部なんて。ま、 “くノ一( くのいち )” だったら話は別なんですが、ところで、どうしてギャル系忍者のことを “くノ一” というか知ってますか?僕は知ってます。知ってはいますが、誰でも知ってる話なので、敢えてここには書きません。誰でも知ってることを自慢気に書いてみたところで、「んなの、誰でも知ってるぢゃん。」…と、馬鹿にされるのがオチですもんね。自慢したいことを馬鹿にされることほど、世の中で不快なことはないんですが、あ、そうそう。手裏剣を投げる以外にもうひとつ、忍者が得意なものがありました。それは何かというと、 “撒き菱を撒く” という技なんですが、それはいったいどういう技なのかというと、菱の実を巻き散らかすという、ただそれだけのものなんですけどね。菱の実というのがいったいどのようなものなのか、実際に目にしたことはないのでよくわからんのですが、恐らくまあ、菱形をしているのではなかろうかと。で、菱形というのは尖った部分があるので、踏んづけるとむっちゃ痛いやん!…と、ま、そのような効果があるわけでありますな。
天然の菱の実を使うのではなく、それを模した鋼鉄製の “巻き菱” というのも考案されております。形状としてはまあ、テトラポットにトゲトゲを付けたものと思っていただければよろしいかと思いますが、どう転んでもトゲトゲの部分が上になるように工夫されているようです。これはもう、何だかとっても効果がありそうですよね。で、他に忍者が駆使する道具にはどのようなものがあるのかというと、例えばえーと、 “鉤縄” だとか。これはおそらく縄の先にカギ状の錘(おもり)を付けたようなものであると思われ、用途としては高いところに引っ掛けて壁によじ登るとか、人を目掛けて投げつけて縄で絡めて足元をすくうとか、ま、やろうとしていることはワカランでもないんですが、実際問題、そんなうまくいくか?…という気がしないでもありません。投げても投げてもうまく引っかからず、そのうち、イーッ!となって、「もういいっ!やめるっ!」…と、投げ出す破目になるだろうことは必至。世の中、忍者が考えているほど甘くはないわけでありまして。で、同じく、その実用性が大いに疑問視される忍者グッズに “水蜘蛛” というのがありますね。これは何かというと、水の上を自由自在に歩き回るための道具なんですが、仕組みとしてはとっても簡単。靴に小さな浮き袋を付けたら、水に浮かんで歩けるんじゃないかな?…って、いやこれは、ほとんど小学生レベルの発想でありますな。よくいますよね、こういう小学生。「水の上を自由自在に歩ける画期的な発明や!」…とか言って、学校の授業で使うビート板を半分に切って、ガムテープで運動靴に貼り付けたりして。取り巻きの子供たちも最初のうちは、「おおっ、タカシくん、すげぇ!」…とか言って感心してるんだけど、いざ、ため池の上を歩き始めたら瞬時に水没して、「ぜんぜん駄目ぢゃん!」…と、大いに信用を落とす結果に終わることは必至。ランニングから、短パンから、グンゼパンツまでべちゃべちゃになるわ、鼻の穴から思いっきり池の水を吸い込むわ、そばで見ていた好きだった佳代ちゃんからは軽蔑されるわ、ビート板を駄目にしてお母さんからは叱られるわで、いいことなんかひとつもありません。よい子はけっして真似をしてはいけませんね。
…とまあ、忍者の “水蜘蛛” というのもタカシくんの愚行と似たようなものでありまして、あんなもので水の上を歩けると考えるほうがどうかしておりますな。タカシくん同様、水に入った瞬間に水没しちゃうのが関の山でしょう。ま、よしんば、物すごく浮力のある “水蜘蛛” を発明したとしても、それで水の上を歩くというのは非常に困難だと思われます。バランス悪過ぎですよね、ありゃ。 水に沈むことはないにしても、一歩前に出ようとした瞬間に大コケして、で、なまじ浮力があり過ぎるものだから足を上にした状態で水中に宙吊りになって、5分で溺死でありますな、おそらく。だいたい、そんな苦労をしてまで水の上を歩くだけの必然性はないわけでありまして、ゴムボートを使えばいいぢゃん。…と思わずにはいられません。 そうか!その手があったか!…ということに気が付いて、忍者という職業は急速に廃れていったのでありました。おしまい。
ということで、今日はウエス・モンゴメリーです。しかし何ですな。忍者の戦法というのはよく考えると、暗闇から手裏剣を投げつけたり、道端に巻き菱を巻き散らかしたりして、やってることが今ひとつ姑息ですよね。もうほとんど、教室の後ろの席から紙つぶてを投げつけたり、椅子の上に画鋲を置いたりする子供と同レベルでありまして、男なら正々堂々、真正面から勝負しろよ!…と言いたくなってしまいます。ま、ゲリラなんだから、しょうがないぢゃん。…という意見もあろうかとは思いますが、ゲリラだから下痢をしてもいいということにはなりませんからね。いや、ぜんぜん関係のない話だし、ゲリラにだって下痢をする権利はあると思うんですけど。とまあそんなことで、 『ポートレート・オブ・ウエス』 です。何だか今ひとつ地味なアルバムではありますな。ジャケットのデザインも地味、ギター・オルガン・ドラムスという編成も何だか今ひとつ地味。ソソられるものはあまりないんですが、粗相をする虚無僧というのは、ちょっぴりソソられるものがありますな。いや、かなりマニアな趣向だとは思うんですけど。ということで、では1曲目から聴いてみることに致しましょう。
えーと、まずは 「フレディ・フリーローダー」 でありますか。マイルスでお馴染みのナンバーでありますが、というか、マイルスのオリジナルみたいなんですが、この曲の名前がどうしても覚えられないという人は、パンツを脱いだらフリだいっ、フリでどうだいっ。…というのに、何となく名前が似ている曲。…と記憶しておくといいと思います。いや、何もそんな無理な覚え方をしなくても何とかなるようなタイトルだとは思うんですけど。しかしこのアルバムはサイドマンも何だか地味でありますな。オルガンのメル・ラインというのは、片仮名表記がそれで合っているのかどうかわからないくらいよく知らない人だし、ドラムスのジョージ・ブラウンに至っては、全米各地に100万人くらいはいそうなくらい、ありきたりな名前ですよね。ジョージ・ブラウンというのは、とってもスイートな人でしたっけ?いや、違いますね。それはジョージア・ブラウンですね。ジョージ・ブラウンのほうはアレです。山本譲司をうんと茶色にしたような人。そういうキャラなのではないかと思われます。日本でもよく見かけますよね、そういうタイプの人。 で、演奏のほうはと言うとですね、これまた何だか、とっても地味でありますな。ギターによる短いイントロに続き、オルガン主導でテーマが演奏されるんですが、何だか今ひとつ迫力不足の感は否めません。すんげぇデカい台風や!…というのでみんなビビって、塗装屋さんなんか今日のお仕事を休んじゃった程なんですが、いざ来て見たらぜんぜん大したことなかった台風22号みたいな感じぃ?いや、当初の予想より進路が東寄りになったせいで、ウチのほうではまるっきり期待はずれ…というか、いや、台風の被害にあまり期待をしてはいけないんですが、もうちょっとこう、派手に暴れてくれるものだとばかり思っていたんですよね。直撃コースとなった関東のほうはどうだったんですかね?
で、テーマ自体はシンプルで極めて短いものなのですぐに終わってしまって、続いてはウエスくんのソロでありますか。いや、このプレイは悪くありませんね。派手にオクターブ奏法やコード奏法を駆使して、もうノリノリぃ♪…という感じではなく、どちらかというと淡々とした立ち上がりなんですが、弾いているうちに次第に調子に乗ってきて、銚子市内でキッコーマンって感じぃ?いや、僕はどちらかというと醤油はサンジルシ派なんですが、首都圏での知名度は今ひとつですからね、サンジルシ。桑名の辺りでは “サンジルシ球場” というのもあったりして、けっこう頑張っているんですけどね。などと言ってるうちにギターのソロは終わっちゃいましたが、続いてはメル・ラインのオルガンでありますか。この人がいったいどういう人であるのか、今ひとつよくわからなかったのでちょっと調べてみたんですが、ほほう、なるほど。ジャズ・オルガンをやってる人だったんですね。いや、それくらいのことは調べる前から何となく検討はついていたんですけど。あとは、えーと…、よくわかりません。ウエスの 「ボス・ギター」 にも参加しているみたいだから、ウエスとは仲がよかったんでしょうな。仲良きことは美しいことだと思います。が、肝心の演奏のほうはというと、オルガンにしては今ひとつ押しが弱い感じがありまして、相撲で言うと四つ相撲、寿司で言うと押し寿司よりも握り寿司が得意なタイプなのではなかろうかと。いなり寿司なんかも美味しいですけどね。で、ギターとドラムスの4バースがあってそこそこ盛り上がって、テーマに戻って、おしまい。
で、2曲目です。 「ロリータ」 ですか。よいですな。ロリ好きですからね、僕って。塩サバ物産(仮名)の津営業所では、 「いなばさんって、女子高生が好きなんですよね?」 …という誤った噂が広まっているようですが、決してそんなことはありません。女子中学生だってOKです。小学生だって、5年生くらいなら大丈夫?…という気がするくらいでありまして、いや、逆に年上だってぜんぜん大丈夫なんですけどね。女子大生から20代前半くらいまでの範囲がちょっと苦手かな?…という気はするんですが、ストライクゾーンはかなり広めであります。いなばくんは女子高生も好き。…と、訂正して頂きたいと思いますね。で、この曲、どこかで聴いたことがあるんだよね。そう、このラテンのノリ。…と思っていたら、バリー・ハリスのオリジナルだったんですな。なるほど、言われてみれば、 『アット・ザ・ジャズ・ワークショップ』 で演奏されていた曲でありますな。で、その曲をですね、ウエスとメル君はラテンのリズムでミディアム・テンポでスインギーに料理しております。テーマ部はギターとオルガンのユニゾンですな。で、その後、ウエスのソロになるんですが、ここではかなりオクターブ奏法を駆使して、張り切っているように見受けられます。幼女にいいモノを見せたい。そういう魂胆なのでありましょう。ほらほら、お嬢ちゃん、いいモノを見せてあげようかぁ?えへえへえへ♪…って、いや、そういう気持ちはよくわかりますよね。ま、僕はロリ系でも、あまり幼すぎるのは駄目なんですけど。で、続いてはメル君のソロでありますな。ま、地味なりにスインギー。そういうことは言えるかも知れませんね。ただ、ギターとオルガンのソロの間もバックのリズムがずーっとラテン調なのはどうか?…という気がしないでもなくて、いや正直、ちょっぴり耳障りなんですよね。テーマ部はラテンで料理して、アドリブ・パートに入ると4ビートに転じる。…というパターンが個人的には好きなんですが、ま、ジョージ・ブラウン君が、「どうしても最後までラテンでやるぅ!」…と駄々をこねた以上、他人が口を挟む余地はないわけでありまして。
ということで、3曲目です。 「ブルース・リフ」 。ウエス君のオリジナルなんですが、これはアレですよね。ブルースなリフ・ナンバー。ま、おそらくそんな感じの作品なのではなかろうかと。…と思っていたら、案の定そんな感じの作品でありました。テーマ自体は極めてシンプルなリフ・ブルースでありますな。そこを出発点にしてウエスが自由自在・変幻自在・観自在菩薩なアドリブを繰り広げるわけでありますが、僕の持っている輸入盤CDにはこの曲の別テイクが連続して収録されていて、同じ曲を続けて聴かされるハメになって、うざい。…と、そんな感じがしてしまいます。自在だけど、うざい。そういう1曲でありますな。いや、ウエスには何の罪もない話なんですけど。で、そろそろ書くことがなくなってきたので、原文ライナーでも見てみようかと思うんですが、えーと、この曲に関しては何も書かれておりませんでした。ただ、 「ムーヴィン・アロング」 はシンプルなスケールをベースにしているが、決して “monotonous” ではなくて、ギターとオルガンのグッドなソロがフィーチャーされるうんぬん。…という記載があって、ダン・モーゲンスターン君が曲名を勘違いしているのか、あるいは 「ムーヴィン・アロング」 と 「ブルース・リフ」 というのは異名同曲なのか。その辺りの事情は部外者である僕には今ひとつよくわからんのですが、ちなみに “monotonous” というのはちょっと調べてみたところ、「単調な、一本調子の」…といった意味であるようですね。要するに、シンプルではあるが単調ではない。そういうことをダン・モゲ君は言いたかったのだと思います。僕もそう思います。で、4曲目は 「ブルース・リフ」 でありますか。どこかで聴いたことがのあると思ったら、3曲目と同じではありませんか。だから別テイクはうざいちゅうねん!…と思わずにはいられませんが、別テイクを無視した4曲目は同じくウエスのオリジナルで、 「デンジャラス」 という曲じゃらす。いいですよねぇ、 『デンジャラス・トイズ』 。いや、そういうタイトルの裏本があるんですが、モデルがけっこうロリ系なんですよね。評判がよかったのか、同じモデルで 『ほたる』 という続編も作られているんですが、こちらのほうはちょっとだけ大人びた感じになっておりました。それはそうとこの 「デンジャラス」 という曲、なかなかよい感じの仕上がりでありますな。さほどデンジャラスな雰囲気はなくて、どちらかというと “ほのぼの系” なんですが、ファンキーな味わいがあって、ヤンキーな味わいはなくて、そこのところがとってもいいと思います。苦手ですからね、ヤンキー系のぎゃる。 『ヤンママはAVアイドル』 というタイトルのDVDは、ちょっといいかな?…という気もするんですけどね。幼く見えるあの娘も実は人の妻。イマドキ女子校生の早熟物語!!…というキャッチフレーズは、かなりソソられるものがありますな。ただ、 “女子校生” という書き方はあまりよくありませんね。世の中には女子校ではなくて共学校や男子校に通っている女子高生もいるわけでありまして、いや、男子校に通っている女子高生というのはあまりいないかも知れませんが、僕はやっぱり “女子校生” よりも “女子高生” という書き方のほうが好きっ♪
ということで、5曲目です。ここらでひとつバラードを聴いてみたいな。…という気分だったんですが、ちょうどいいタイミングでスロー・ナンバーを持ってきましたな。 「イエスタデイズ・チャイルド」 というのは和訳すると、 「昨日の子供」 ですかね?どうしてそのようなテーマで歌を作ろうと思い立ったのか、その辺りの事情は部外者である僕には今ひとつよくわからんのですが、作曲したのはチャールス・デフォレストという人のようですな。が、原文ライナーには、ウエスによるプリティなバラード…てなことが書いてありまして、この辺り、ダン・モゲ君の書いてることには今ひとつ信憑性がないというか、カンピョウは栃木の名産であるというか。ま、ウエスが演奏するところのプリティなバラードという意味なのかも知れませんけど。で、いざ聴いてみると、確かにしみじみとしていて悪くないとは思うんですが、ちょっぴり展開が単調で、退屈な感じがしないでもありません。ここらでひとつバラードを聴いてみたいな。…というリクエストは失敗でしたかね?ということで、最後はパーッと派手に締めて欲しいところでありますが、アルバムのラストを飾るのは、ご存知、ボビー・ティモンズのヒット曲、 「モーニン」 でありますか。あまりにもベタな選曲ではありますが、なかなか興味深いというのも事実であります。で、ウエス版 「モーニン」 の出来はどうかというとですね、うーん、まあまあですかね?ウエス君のソロもそれなりにノリがよくて、悪くないとは思うんですが、やはりこの楽器編成では迫力不足の感は否めません。でもまあ、これはこれで悪くないかな?…という気がしないでもないんですけどね。で、僕の持っているCDには、最後に 「モーニン」 の別テイクが入っているんですが、そんなものはどうでもよくて、最後はとっても “モーニン” な1枚なのでありました。ニンニン。
【総合評価】
評価の難しいアルバムですな。いいか?…と聞かれると、それほど極め付けにいいわけでもないし、じゃ、悪いのか?…というと、そう決め付けてしまうには勿体ない1枚ではあると思います。一言でいうと、地味。そんな作品だと思いますが、通のウケは意外といいかも?