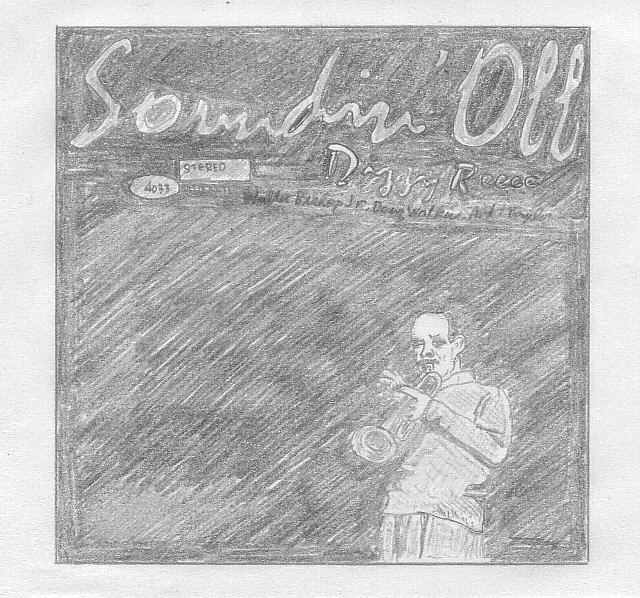
今日は 「お土産ともみあげ」 というテーマでお届けしたいと思います。が、“もみあげ”のほうはまったくもってどうでもいいような気もしますね。相撲取りの闘牙はモミアゲが長いです。おしまい。…って、それだけ書いたらネタが尽きちゃいますもんね。お土産と絡めてみたところで話がそれ以上に進展するとも思えません。お土産に“モミアゲの切ったの”とか貰っても、あまり嬉しくはないですよね。というか、迷惑ですよね。「どないせえちゅうねん!?」と言いたくなっちゃいますよね。そこでまあ、今回はモミアゲのほうはヤメにして、“お土産”一本で勝負しようと思うんですが、僕はお土産に関してひとつの疑問がございます。それは何かというと、「どうして“土産”と書いて、“みやげ”と読むのか?」ということなんですが、こんなの知らなければ絶対に読めませんよね。いったい “土産” のどの部分が “みや” で、どの部分が “げ” だと言うんでしょうか?あるいは、いったい “土産” のどの部分が “み” で、どの部分が “やげ” だと言うんでしょうか?それにくらべると“鼻毛(はなげ)”なんかは単純明快ですよね。“鼻毛”の場合、“鼻” の部分が “はな” で、“毛” の部分が “げ” ですもんね。“土産”には、“鼻毛”の潔さを見習え!…と文句のひとつも言いたくなってしまうところでありますが、これはおそらく、中国から伝わった漢字に、古来から日本で用いられていた“倭言葉”の読みを無理矢理当て嵌めたところに問題があったのだと思われます。そもそも中国ではいつ頃から“土産”という言葉が使われたのかというと、唐時代に活躍した詩人、李白の『台湾遊戯』という七言絶句がその起源であると言われております。
我 挙 行 台 湾 旅 行
購 入 淫 売 現 地 娘
元 気 溌 剌 大 興 奮
土 産 毛 虱 嗚 呼 痒 々
いかにも李白らしい豪放磊落な作風である。…と評価することも出来ますが、あまりにもそのまんまで、何の技法も施されてないぢゃないか。…という気がしないでもありません。結句の部分が字余りになっているんですが、「とても“嗚呼痒”と三文字で表現できるような痒さではなかった。」と語ったとされるエピソードが、李白の人となりをよく表していて興味深いところでありますな。ちなみに李白がここで用いている“土産”という言葉は、我々が今日で言うところの“おみやげ”とは多少意味合いが違っていたようでありまして、彼は“土地のモノ”といった程度の意味でこの言葉を使ったようです。…んとにもぉ、イナカの娘は毛ジラミなんぞを湧かしてからにぃ。…という、多少の侮蔑の思いを込めて“土産”という言葉を使ったわけでありますが、これが中国の知識層の人たちの間で大いにウケたそうであります。唐の都・長安では、イナカ娘の垢抜けなさを売り物にした新しいフーゾク、“土産倶楽部”(←略して“ドサクラ”)と呼ばれる店が大繁盛したというのだから、何をいわんや…といった感じでありますが、今でも田舎興行のことを“ドサまわり”と言ったりするのは、ここにルーツがあったわけですね。以来中国では、珍奇ではあるが何だか垢抜けないイナカの産物のことを“土産”と称して、多少の憐憫の意を込めて用いるようになった次第でありますが、いや、我ながら何だかもっともらしい説でありますなぁ。
さて一方、倭言葉の“みやげ”のほうはと言うと、こちらは元来、崇高な意味を持ち合わせておりました。伊勢神宮は古来より日本人の心の拠り所になっていたわけですが、その“お伊勢参り”に際して、神サマより下賜たまわったもの。例えば、お供えのダイコンの残り物なんぞを庶民は“宮下(みやげ)”と称して、ありがたく家に持ち帰ったそうでありますが、この“宮下(みやげ)”が今日で言う“おみやげ”のルーツになったと言われております。神サマからのおさがりでありますので、本来なら毛ジラミなんぞを“おみやげ”と呼ぶのは不敬の極みであるわけですが、いや、同じ言葉でも中国と日本では、その成り立ちがずいぶんと違うものなんですなぁ。で、当初は“宮下(みやげ)”と表記されていたものが、どうして“土産”という漢字が当てられるようになったのかというとですね、これには歴史に名高い“宮下クンのつぶやき”という事件が深く関与しているのだ。…と言われております。これは一体どのような事件であったかというとですね、ある日、宮下(みやした)クンという青年が何気なく「僕の名前って、何だか“みやげ”みたいだよね。」とつぶやいたのを耳にした弘法大師・空海が「それもそうだ。」と思って、「じゃ、これから“みやげ”のことは中国風に“土産”と書くことにしよう。そもそも中国で“土産”という言葉が作られるようになったのは、唐時代に活躍した詩人、李白の“台湾遊戯”という七言絶句がその起源であるわけであって…」と、放っておけばいつまでもクドクドと薀蓄を傾けたりして、聞いているほうとしても次第に面倒になってしまって、「はいはい、そうですね。これから“みやげ”のことは“土産”と書くようにしましょうね。」と適当に相槌を打ったところ、そのように決まってしまった。…というような事件だったわけですが、空海のカリスマ的な権力を如実に示すエピソードとして密教徒の間ではよく知られております。…って、いや、我ながらまったく説得力がありませんな。いきなり空海が出てくるあたりが何とも胡散臭いですよね。温泉でも橋でも仏像でも高野豆腐でも、とりあえず空海が作ったことにしておけば、何とかなるさ♪…みたいな安易な発想は厳に慎まなければならないと思いますが、ではここで少し“お土産”という言葉の起源について調べてみることにしましょうか。
土産をどうして「みやげ」と読むのか、身近な言葉にも関らず長い間、疑問であった。土産という二つの漢字が視覚的にも、その土地の産物という理解を導きやすい。しかし、みやげとルビをふった時に、この三文字をどのように配分したらいいのかわからない。このことがきっかけとなって、土産についての語源の旅に出ることにした。金田一春彦氏の「日本語」新版(下)から見てみよう。日本語にあっても中国語にあたる言葉がない場合がある。そういう場合に書くべき漢字がない。この場合はどうしたか。適当な漢字がない場合に苦心した方法として考えたのは、熟字訓と言われるものである。「五月雨」と書いてサミダレと読んだり、「時雨」と書いてシグレと読んだりする例がそれである。「紅葉」がモミジであり、「土産」がミヤゲである。何故こういうことが起こるかというと、シグレにあたる中国語がないので意味を考えて、ときどき降る雨だからというわけで「時雨」と書いてシグレと読むことにしたのである。別に「時」をシグと読んだり「雨」をレと読まれるものではない、と解説されている。そうであれば「土」をミヤと読んだり、「産」をゲと読まれるわけではないということになる。そしてもともと日本語として「みやげ」という言葉があったことになる。
…と、長々と引用してしまいましたが、ここまでの論点は金田一春彦も僕も、まったくと言っていいほど同じであると言ってもいいですよね。で、さらにこの“JTBおみやげネット”というサイトにはこのような興味深い説も紹介されておりました。
宮笥(みやけ)を語源とする説をもう一つ紹介すると、三重県伊勢市に「せきや」という老舗がある。 ここはあわびやさざえの脹煮の専門店だが、その商品のなかに宮笥(みやげ)という珍味がある。「せきや」のパンフレットによると、宮笥とは土産の語源。お宮さんで頂戴した箱という意味がある。土産はまた伊勢神宮参拝の祈りに行けない人が餞別を託して参拝を頼み、お札やお守りなどを、買ってもらって帰ったのが、今日の土産のはじまりといわれている、と案内されている。
これはもう、僕の“宮下(みやげ)説”とニアピン賞であると言い切ってもよいのではなかろうかと。我ながら自分の論調の鋭さに、思わず自分で自分に浣腸したくなったほどでありますが、他のサイトには 「おみやげの語源は“お宮下”です。これは、もともとお米をお宮に献上したものを、神社や寺院では参道の茶店などに払い下げ、たとえば餅などに加工して参拝者の帰路の食料にしていたことから来ています。現在においても“米”などを原料にした食品が、おみやげとしての商品に多いのはそのためのようです。」 という、ずばりビンゴと言ってもいいような説も書いてありました。いやあ、僕の単なる思いつきも、まんざら捨てたものではありませんな。空海や宮下(みやした)クンこそ登場しないものの、“おこめ”が出てくるあたりは李白の台湾遊興における毛ジラミ問題との関連性も予感させ、興味深い一説であると言えましょう。ということで、お土産の語源がなんとなくわかったところで、続いては“お土産選びのポイント”という問題に話題を転じてみようと思うんですが、お土産選びというのはその人のセンスが試されるようなところがありますよね。例えば、某レーザー技士のようにスイス出張のお土産に“ピンクゴッド”を買ってきたりすると、その人の品位が激しく問われることになってしまいます。“ツインゴッド”だったらよかったのにぃ。。。ま、会社に買ってくるお土産というのは無難路線がイチバンでありまして、例えば京都だったら“生八橋”あたりが手堅いですよね。ディズニーランドだったら“ミッキー最中”とか“ミミー煎餅”あたりが差しさわりがなく、スイスのレマン湖あたりなら“レマン湖まんじゅう”、略して“れまんじゅう”なんてのが、おばさま方には喜ばれようかと。“もっこり大将”などのグッズも、いや、キノコ類栽培セットなどもおばさま方のウケはよかったようですが、やはりみんなで分けることが出来るという点ではお菓子の類のほうがOLさんには有り難がられますよね。
ただこの際に注意しなければならないのは“必要な人数分”を確保するということでありまして、確かウチの事務所って全部で12人だったよね?…と思って12個入りの温泉饅頭を買ってきたのはいいんだけど、月曜日に出社してみたら、もう1人おったやん!…ということに気がついた。…という経験は誰にでもあると思います。もの凄く存在感の薄いヤツって、どの会社にも必ず1人くらいはいますからね。僕なんかもよく、「あれ?おったん?」とか言われちゃうタイプなんですが、こういうヤツに限って存在感はないくせに妙にプライドは高かったりするので、1人だけ温泉饅頭を買い忘れちゃったりすると、ものすごくイジケます。必ずイジケます。で、嫌味ったらしく自分で和菓子屋さんに行って、そこでいちばん高い饅頭をひとつだけ買ってきたりします。そして、「やっぱりお土産の安い温泉饅頭なんかと違って、高い高級饅頭はオイシイなぁ。」と、聞こえよがしに呟いたりします。これではせっかく温泉饅頭を12個も買ってきた下柳クン(27歳)としても、立つ瀬がないですよね。僕たちはこの“下柳の悲劇”を教訓に、会社にお土産を買ってくる場合には頭に浮かんだ人数よりも3人分程度は余計に買ってくるべきである。…ということを学んだわけでありますが、ま、余った分は存在感がないくせに妙にプライドだけは高いヤツにでもくれてやってくださいね。こういうヤツはプライドは高いくせに根は極めて単純なので、「僕だけ饅頭が2個もあるー。もしかして僕って、惚れられてるぅ?」と勘違いしたりして、ま、本人がそう思っているのなら、それはそれで幸せなことではないですかー。
ちなみに僕の場合、会社にお土産を買ってくる場合には個数以外にも次のような点に注意するようにしております。
その1 : 個別舗装であること。
その2 : どこのお土産であるか一目でわかること。
その3 : 洋菓子系であること。
いや、温泉饅頭などの和菓子系というのは、何だかヤングなギャルにはウケが悪そう?…というイメージがありますよね。個人的には“和菓子好きギャル”というのは風情があって悪くないと思うんですが、「いなばさんは饅頭なんか買ってきて、ああ見えて意外とおっさん臭いのね。」などという風評が立ったりしたら、心外ですもんね。で、“個別舗装”というのもOLさんに余計な手間をかけさせないためのポイントでありまして、例えば温泉饅頭なんかはいちいち菓子皿に取り分けて配分しなければならないので、「いなばさんは饅頭なんか買ってきて、こういうのって配るのが面倒で有難迷惑なのよねぇ。」などという悪い評判が立ちかねません。いちいち切り分けなければならないカステラ状のものやスイスロール状のものも避けたほうが無難でしょう。こういうのは饅頭以上に面倒ですからね。そこでまあ、個別包装のクッキーの類が無難なんぢゃないか?…という気がするんですが、ここで問題になってくるのは(その2)の“どこのお土産であるか一目でわかること”という点でありまして。せっかく八方まで行ったのだから、「まあ、いなばさん、八方に行ったのね。スキー上手なのね。」と思われたい。…と願うのは当然のことでありまして、ここは是非、一目で八方に行ったことがわかるようなもの、例えば『月亭八方の香り』(←基本)とか『八宝菜のもと』(←基本)といったお土産を持って帰りたいと思うわけです。ま、“八方”の2文字が無理だとしても、せめて“白馬”の文字は確保したいですよね。『白馬の白い馬』とか。が、ここで注意をしなければならないのは、最近では“箱だけ白馬”といった商品がほとんどである。…という事実認識でありまして、つまり、外箱には確かに『白馬の白い馬』という名前が書いてあるんだけど、個別包装には“ミルククッキー”などという曖昧な名前しか書いてない。…というパターンでありますな。すなわちこれは、外箱さえ変えればどこのお土産としても通用する。…という、とってもフレキシブルな商品でありまして、極端な話、中身としてはまったく同じ商品が『長良川鵜飼クッキー』として岐阜駅前で売られていることも考えられるわけです。ま、一応のところ製造者は長野県内の業者になっているから、県外まで出張ってくることはないと思うんですが、『軽井沢の軽い沢』という名前で軽井沢駅前で売られている可能性は多分にありますよね。こういう、いい加減な商品はいかん!…と、潔癖症である僕は思ってしまうわけです。そこでまあ、“安曇野スイス村”で15分ほど悩んだあげく、中袋にまできちんと『白馬のなんたら〜ラング・ド・シャ』と書かれた15個入りのお菓子(←ウチの事務所は総勢13名)を買ったんですが、持って帰る途中でリンゴ(6個入り500円)に圧迫されてドシャっと潰れてしまい、仕方がないので自分で全部食べました。今年2月のちょっと切ない思い出でございます。そんだけ。
ということで、ディジー・リースです。いや、今日のネタの後半は何だか取って付けたような感じになってしまいましたが、当初は“のしいか”の話をどこかに絡ませようと思っていたんですけどね。ほら、僕ってコドモの頃、お土産と言えば必ずといっていいほど“のしいか”買ってたしー。今から思えば“のしいか”なんてものは手でちぎって食べようとすると指先がネチネチしてうっとうしいだけだし、大して美味くもないし、おまけにイカ臭いやんけ!…というので、決して誉められた食べ物ではなかったような気がするんですが、何故、憑かれたかのように“のしいか”なんか買っていたんでしょうね?…というところから話を進めていこうと思っていたんですが、ま、大したネタでもないので別にどうでもいいんですけどね。さてそこでディジー・リースです。確かイギリス出身のトランペッターで、頭が若干ハゲている。…というのが僕がディジー・リースについて知っていることの全容なんですが、確かブルーノートに3枚ほどリーダー作を残しているのではなかったかと。中でも『スター・ブライト』というアルバムはサイドマンにハンク・モブレイやウイントン・ケリーが参加していることもあって、ちょっとした人気盤にもなっているほどなんですが、今日のは地味です。『サウンディン・オフ』。ほら、名前からして何だか地味ですよね。あまりに地味すぎて名前が覚えられない。…という人は“触っていい?お麩”と覚えるといいと思います。いや、お麩なんてものはいちいち了解を得なくても、どんどん勝手にサワっちゃえばいいような気もするんですが、「お麩にサワってはいけません。」と、厳しく躾けられた家庭で育った子なのかも知れませんね。で、このアルバムはジャケットのセンスも今ひとつでありますなぁ。ちょっぴり頭のハゲたおじさんがトランペットを吹いてる図。…って、BN盤には極めてありがちな構図なんですが、まったくもって訴えかけてくるものがございません。モデルに“華”がないというのか、“毛”がないというのか、いや、両サイドにはきちんとあるんですが、一層のこと、額から上の部分をトリミングしてウィーク・ポイントを隠蔽したほうがよかったのではないか?…という気もするんですが、ま、アタマの全貌を写してしまったものはしょうがないしー。で、トランペットのワン・ホーンという編成も地味ですね。何かこう、まったくソソられるもののない1枚なんですが、僕が持っているアルバムの中でまだ紹介したことがないのはこの1枚だけだしー。ということで、あまり気乗りはしないんですが、とりあえず1曲目から聴いてみることにしましょう。
まずは「ゴースト・オブ・ア・チャンス」です。何の前触れもなく、いきなりトランペットによるテーマで始まるというのは、ある意味、新鮮ではありますな。最初の1音は無伴奏で、んでもって、すぐにリズムが入ってきて、しみじみとしたバラード演奏になるわけでありますが、ここらあたりの演出は実に小粋な感じがして、悪くありません。やるな、ハゲ!…といったところですね。いや、「ハゲでも、やる時はやる。」というのは知識としては持ち合わせていても、なかなか実感がわかないのが実情ですからね。で、トランペットのワン・ホーンというのはよほど実力がないと、マヌケになるか、パッとしないかのどちらかになっちゃう可能性が 非常に高いわけでありますが、最初にバラードを持ってきたというのは、なかなかの見識だと思います。スローな曲だとワン・ホーンでも、その場のムードで何となくうやむやのうちに 最後まで聴かせることが出来ますからね。どんな安っぽいギャルでも、店の暗ぁ〜い照明の元だと、それなりに見える。…というのと似たところがあるわけですが、えーと、ここまで来て早くも書くことがなくなってしまったので、とりあえず原文ライナーでも見てみることにしましょう。完成されたフレーズと言ってもいいような、長く引き延ばしたオープニングの1音で、思い入れたっぷりなディジー版 “ア・ゴースト・オブ・ア・チャンス” は幕を開ける…ですか。なるほど、さすが本職だけあって、うまいこと書くもんですな。伊達にウルトラ怪獣みたいな名前をしてるわけじゃねーな、アイラ・ギトラー。…といったところでありますが、確かにこの演奏は最初の1音だけで、勝負アリ。…という感じがしますもんね。で、僕はディジ・リーのバラード演奏に出尻的な美学を感じましたね。とかく“小尻”がもてはやされている昨今でありますが、僕はやっぱりコンビニの寿司は今ひとつだと思いました。いや、僕は今、高山にいるんですが、少し街から離れたところにあるホテルに泊まってるので“タイムリー”(←本部が高山にある岐阜ローカルなコンビニ)で握り寿司を買ってきて食べたんですが、どうも今ひとつでありましたな。おとなしく“助六”くらいにしておいたほうが無難でしたかね?あ、ちなみに“タイムリー”の名誉のために言っておきますが、ここのサンドイッチは美味しいです。で、演奏のほうはというと、ディジ・リーのプレイはあまり技巧に走らず、非行にも走らず、とっても誠実な感じがして、とってもいいと思います。ヘッドフォンで聴くと、何だか切なげに息継ぎをする声が鮮明に聞こえてきたりして、ちょっぴりドキドキしてしまいます。でもジャケットの写真を見ると、そんな気分も一瞬にして萎えてしまいますけどね。で、ディジー…というとガレスピーみたいだし、リースというと、何だかわからないけど壁にかける飾りみたいなもん。…というイメージがあって、どうにも呼び方に困るんですが、とりあえずこのおっさんの演奏も悪くないんですが、中間部で聴けるピアノのソロが、これまたなかなかイイ感じなんですよね。ケリーでもないし、ドリューでもないし、もしかして、トミ・フラあたり?…と思っていたら、実はウォルター・ビショップ・ジュニアだったんですな。日本語ライナーで吉岡祐介という人が、“ガーランドもどきの耽美的なブロック・コードを多用うんぬん”ということを書いておりますが、まさしくそんな感じです。ちょっぴり硬派なパウエル派。…というイメージとはちょっと違った演奏を聴かせておりますが、ま、それもまた人生。
で、2曲目の「ワンス・イン・ア・ホワイル」は、そのビショップの耽美的なピアノのイントロで幕を開けます。またしてもスロー・テンポです。結局これって、バラード集なわけ?…と思っていたら、ディジー・リースが登場したところでテンポが速くなって、ミディアム・テンポの歌モノ。…といった感じに転じました。ディジー・リースって結局のところ、この手の歌モノを吹かせた時がいちばん味わいがありますよね。アート・テイラーのきっちりとした楷書的なドラミングが耳に心地よく、甲斐性なしのディジーも、思わずウキウキ♪…って、自分でも何を書いているのかワケがわかんなくなってきましたが、ちなみに、ここでのビショップのプレイは“ガーランドもどきの耽美的なブロック・コードを多用”の典型例でありあますな。よく転がるタッチが耳に心地よく、それにしてもこのホテルの“すけべビデオ”の今日のプログラムも「淫熟艶女GP」とか「変態不倫妻」とか「豊満三十路乳」とか「乳汁奥様コレクション」とか「特選ミセスショップDX」とか、最近は“ミセス&熟女路線”がブレイクしてるんですかねぇ。。。で、3曲目は「エブ・パッブ」という、今ひとつ発音しにくい曲なんですが、それにしてもこのホテル、一泊4,950円で格安だと思って喜んでいたら、税金と駐車料金310円で結局のところ5,500円になってしまい、おまけに“テレビカード”で1000円取られたから、ちっともリーズナブルではなかったですなぁ。ま、国道沿いにあって場所がわかりやすく、駐車場も広くてとめやすかったから別にいいんですけどね。部屋も小綺麗で便器にはちゃんとウォッシュレットも完備されておりますが、部屋に冷蔵庫がないのが今ひとつだと思います。で、どういうわけだかズボンプレッサーが完備されておりまして、「レバーを開けて開き、パンツをセットする。」と説明書きにありましたので、とりあえず紺のトランクスをセットしておきました。12分で仕上がる模様です。で、で、3曲目は「エブ・パッブ」という、今ひとつ発音しにくい曲なんですが、これは 「アイ・ガット・リズム」を思わせるファッツ・ナヴァロとレオ・パーカーの作品…ということであります。いわゆるバップ曲でありますな。だったら曲名も「エブ・バップ」にしておけばいいようなものを、敢えてそうしないところがバップの真髄なのでありましょう。が、パソコンの画面上では濁音も半濁音もほとんど同じように見えてしまって区別がつけにくいので、わざわざ凝った名前を付けた俺がバカだった。…といった気がしないでもありません。「俺、馬鹿ぁ?」という、レオ・パーカーに捧げられた短句もありましたしね。で、これはファッツのオリジナル・レコーディングを聴いて以来、ディジーが演奏し続けている作品だそうでありまして、メロディをもてあそぶ彼の奔放さも、おそらく曲との長いつき合いの産物と解釈すべきだろう。…と、ギトラーくんは指摘しております。会社の中に必ず一人くらいはいそうですけどね、顔面がギトギトと脂ギッシュで、OLさんから“ギトラー”と呼ばれているおじさん。あ、パンツのプレスが出来あがりましたね。パリっと折り目がついて、なかなか折り目正しい感じに仕上がりました。ブリーフではこうはいかんでしょう。やっぱりパンツはトランクスに限るなぁ。…と再認識した次第でありますが、演奏のほうはバップ…といってもテンポはミディアム・ファスト程度でありまして、ディジーの演奏からは凄みよりも、ほのぼのとしたムードがたちのぼっております。心の底から湧きあがるような自然なフレージングがとってもいいと思います。ウォルター・ビショップもさすがは“根はバッパー”だけあって、ツボを押さえたプレイを聴かせております。…と、無難な感想を書いておいてと。
で、4曲目は「イエスタデイズ」ですね。根はバラードなんですが、ここでのディジ・リーはミディアム・テンポで料理しております。イントロでピアノを弾くビショップが、とってもパウエル的なのが面白いですよね。わはははははは。…と思っていたら、原文ライナーにもきちんと、“バド・パウエルの作品「バウンシング・ウィズ・バド」のブリッジ部分を参考にしている。…と書いてありました。で、ここでのディジー・リーズのプレイは、まあまあです。で、ここでのウォルター・ビショップのプレイは、かなり変です。わはははははは。…と思っていたら、原文ライナーにもきちんと、“ビショップは右手のアタックでソロを開始し、やがてファンキーなコード弾きへと移っていく。かなり熱のこもったプレイではあるが、やり過ぎにはなっていない…って、あ、これは誉め言葉だったんですな。僕としては、「これはやり過ぎである。」と思ってしまったわけなんですが、いやあ、今日のギトラーと僕とはよく意見が合いますなぁ。…と思っていたら、そうでもなかったですね。ギトラー、たいしたヤツではないです。で、5曲目はガーシュインの「我が恋はここに」。僕はこの曲がさほど好きではないので、ディジーの演奏がどうであろうが、別にどうだっていいです。ミディアム・テンポで、無難な感じに仕上げております。で、特筆すべきはアート・テイラーの切れ味鋭いシャープなドラミングですね。ひとつ間違えば、やり過ぎスレスレ…といったところなんですが、きっちりとした叩きっぷりが、ややもすれば緊張感に欠ける嫌いのあるディジーのトランペットをキリっと引き締めておりますな。しかしなんですな。せっかく12分もかけてプレスしたパンツでありますが、5分も穿いているうちにすっかり体温でこなれてきて、すっかり元のヘニャパンに戻っちゃいましたな。パンツプレスって、あまり意味がないんじゃないですかね?…ということで、ラストです。「ブルー・ストリーク」はリースのオリジナルでありまして、名前からしてブルース調の曲でありましょう。…と思っていたら、案の定そうでした。リースくん、性格がわかりやす過ぎぃ。ところでこの冬は毎週のように、スキーだ、オフ会だ、すけべビデオだぁ♪…と遊びほうけていた次第でありますが、そうして、やらなければならない仕事をどんどんと先延ばしにしているうちに、いよいよ、のっぴきならないほど追い詰められてきそうな気配が濃厚となってまいりました。来週あたり、マジでやばいかも知れませんなぁ。。。でもまあ、何とかなるよね?…と、努めて平静を装って現実から逃避している次第でありますが、心の底ではけっこうブルーだったりします。で、「ブルー・ストリーク」。ブルースと言っても、なかなか明るく楽しめのナンバーなのでちょっぴり救われた気分にはなりますが、やっぱり心は今ひとつ晴れませんなぁ。外は雨だしぃ。こうなったらもう、“むき栗”食ってやるぅ!
【総合評価】
えー、派手ではないが、頭はハゲてる。そういう人でありましたな、ディジー・リースは。ゆったりしたテンポの演奏が中心で、心が安らぎますなぁ。…と感じる人がいる一方、かったるくて、やってられねー。…と、そのような感想を持つ人もいるかも知れません。ま、いずれにせよ、エレベーターホールにある自販機で“むき栗”(200円)を買ってきました。“歴代皇帝献上品”です。“中国河北省遷西県産”です。“無添加・無着色自然食”です。輸入者は“紫玉ジャパン”です。これはもう、凄いです。さっそく食べてみると…、たいしてうまくもねぇ。。。