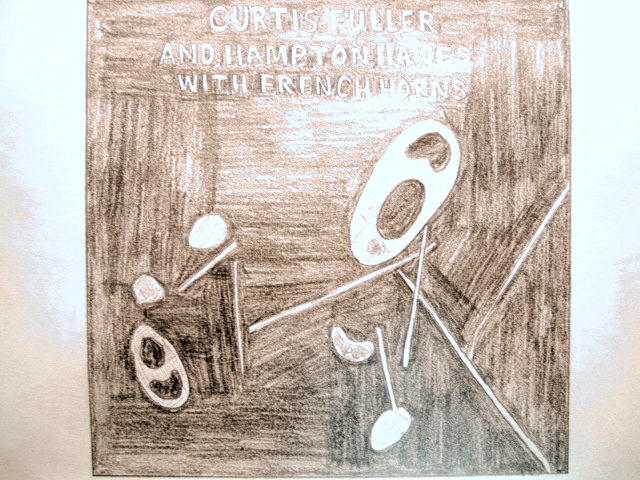WITH FRENCH HORNS (NEW JAZZ)
CURTIS FULLER (1957/5/18)
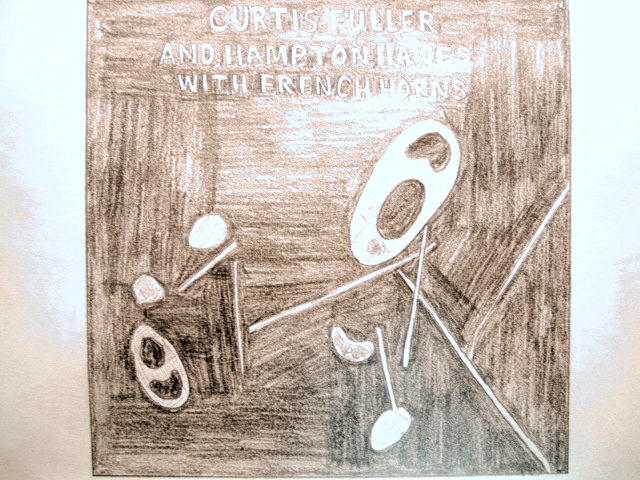
【パーソネル】
CURTIS FULLER (tb) JULIUS WATKINS (frh) DAVID AMRAM (frh) SAHIB SHIHAB (as)
HAMPTON HAWES (p) TEDDY CHARLES (p) ADDISON FARMER (b) JERRY SEGAL (ds)
【収録曲】
RONNIE'S TUNE / ROC AND TROLL / A-DRIFT
FIVE SPOT / LYRISTE / NO CROOKS
【解説】
今日は将棋について考えてみたいと思います。いや今朝、ラジオで将棋の話をしていたので、何となく。
将棋といえばこのところ「俳句傑作選」のページを作るため、過去の作品を読み直しているんですけどね。するとその中に「さんま¥103(税込・仮名)の将棋俳句」というのがございました。いや、今だから白状するんですが、この作品がメールで送られてきたとき、正直言って「どうしようか。。。」と思ってしまいました。結局、貴重な読者を失ってしまうことを恐れて掲載に踏み切ったわけでありますが、勝手に消えちゃいましたけどね、キャバクラ1号(仮名)さん。だいたい「ふ」とか「きん」とか「ぎん」などという将棋の駒の名前は俳句の課題にするのは短すぎるんじゃないか?という気がするわけでありますが、そういえば開催期日がまだ未定である「塩通・春のオフ会」の課題“サンリオ・キャラクター俳句”のほうも失敗に終わる気配が濃厚ですね。ところでオフ会の日程はどうしましょうかね?ごんあじ嬢からは一ヶ月に一度ほど、思い出したようにメールが来るんですが、わざわざ長崎から参加してもらうほどのものか?という気がしないでもないので、とりあえず“ぎゃる抜き”でやっちゃいましょうかね?会場はサンリオ・ピューロランドで決まりですな。
で、将棋。まず最初に僕の将棋に対するスタンスを明らかにしておきますと、スタンスよりも茶箪笥が好き。そういった立場を取るものであるわけですが、将棋なんてものは別に好きではありません。何故かというと、弱いからなんですけどね。人間、誰しも弱いものに関しては好きになれないのが実状でありまして、いや、世の中には「あたし、そこは弱いのぉ♪」というような事態が好きで好きで、たまんない♪といった例外はあるわけですが、将棋に限らず、チェス、囲碁、オセロの類はさっぱりなんですよねぇ、僕って。で、弱いものだからどうしても好きになれないわけでありますが、いや、世の中には「へたの横好き」という言葉もあるんですけどね。「うまのバック好き」とか。いや、あれは別に好きでバックでやってるわけぢゃないんだ。という意見もあろうかとは思いますが、プライドが人一倍高い「負けず嫌いのさばぴょん」、又の名を「国際派ウインドサーファーさば」と呼ばれる僕としては
弱い → 負ける → 悔しい → 嫌い
という経過を持って、「将棋は嫌い」ということになっているわけでありまして。あ、「五目並べ」は割と好きなんですけどね。「五目そば」はあまり好きじゃないんですが、「五目ごはん」は割と好きですしね。「かやくごはん」というのもイイと思うんですが、「座薬ごはん」というのはちょっぴり嫌ですね。経口で服用したところで薬効があるとは思えませんもんね、座薬。ま、消化されずにそのまま肛門に到達することになるわけだから、結果的にはそれでいいぢゃないか。という意見もあろうかとは思いますが、座薬は即効性が命。そんな遠回しなことをしてる暇があったら、ずっぽりと肛門に挿入しちゃったほうが手っ取りばやいと思うんですけどね。
で、えーと「五目並べ」。僕がなぜ「五目並べ」が割と好きなのかというと、それは「白黒がはっきりしている」からなんですけどね。オセロなんか、ちっとも白黒がはっきりしてませんもんね。色が黒いもんだからてっきり見方だとばかり思って安心してたら、ちょっと敵に両側を挟まれたぐらいでいとも簡単に寝返って「白」になったりして、信用出来ないことこの上なし。その点、五目並べはいいですなぁ。黒の石は白のペイントマーカーで塗ったりしない限り、いつまでたっても黒のままですもんね。ちなみにパンツの世界では「白」が圧倒的に優位ということになっておりまして、いくらレースですけすけ♪だろうと、黒のパンツなんてアウト・オブ・眼中であるわけですが、囲碁や五目並べの世界では「黒」のほうがエラいということになっております。なぜ「黒」のほうがエラいのかと言うと、「色が黒いと何となくエラそうに見える。」というのがその理由でありまして、そのことは「黒服」や柔道の「黒帯」の例を見れば明らかなわけでありますが、ではここで「先攻・後攻問題」について話題を転じてみたいと思います。
勝負の世界で、先攻になるか後攻になるかは大きな意味を持ちます。先攻と後攻ではどちらが特か?と言うと、これはもう「先攻が絶対的に有利」というパターンが多いわけでありますが、ただ野球の場合は一概にそうとも言えないところがあるんですけどね。特に延長に入った場合には後攻が有利であると言われるわけですが、いずれにせよ先攻・後攻を決めるには不公平にならないような手段が用いられるのが一般的ですよね。それは例えば「じゃんけん」だったり「コイントス」だったり、将棋の場合は「ふり駒」だったりするわけですね。「ふりちん」という方法もあって、これは「よーいドン!」でパンツの脱がせ合いをして、先にフリチンになったほうがマケ。というルールなんですが、これなんか本編の試合よりも盛り上がったりして、特にギャル系の競技の場合には是非、採用を前向きに検討していただきたいものでございます。あ、ギャルの場合は「フリチン」とは言わないんですかね?
とまあそれはともかく、では囲碁の場合はどのようにして先攻・後攻を決めるのかというと、例えば「ふり石」というのを行ったとしてもあまり意味はありませんよね。「黒い石を5個ずつ手に取って投げ、黒い石の数が多い方が勝ち。」というルールにしたところで、何度やってみても両者は5対5の引き分けで勝負はつかず、それはつまり“やるだけ無駄”ということでございまして。ではどうやって決めるのかというと、結論から申し上げましょう。囲碁の場合、先攻・後攻は最初から決まっております。白が先手です。ではどちらが白を選ぶのかと言うと、これも決まっております。弱いほうが白です。つまりまあ、強いほうは「アンタ、強いんだから多少の不利は我慢しなきゃ駄目だぎゃ。」というシステムになっているわけでありまして、相手に敬意を表することを意味する「一目置く」という言葉はここから来ているわけですね。うん、僕ってなんて物識り。で、先に一目置いたぐらいではどうしようもないくらい実力に差がある場合には一目と言わず二目、三目、四目、五目と先に置くことになるわけですが、ただこの方式はそのまま「五目並べ」に応用することは出来ませんよね。「僕、とっても五目並べが強いから、チミが先に五目ぐらい打ってもいいだぎゃ。」などと余裕をこいてると、いきなり五目並べられて、その時点で敗戦が決定しちゃいますもんね。
ということで、ま、将棋に関してはまた次回。
@
さ、カーティス・フラーです。『カーティス・フラー・アンド・ハンプトン・ホーズ・ウィズ・破廉恥ホルンズ』です。プレスティッジ/ニュージャズ系にこんなアルバムありましたかね?でもまあ、こうしてCDになって輸入盤として売られているわけだから、こんなアルバムもあったんでしょうね。フラーとホーズの共演というのはわりと珍しいのではないかと思いますが、いいですよねぇ、ホーズ。通称ウマさん。彼が「バック好き」であるかどうかはサダカではありませんが、あるいは秘宝館あたりで破廉恥なショーに出演したりしてるのかもしれませんね。ということで、このアルバムにはフレンチホルンも入っております。しかも2本。更にはサヒブ・シハブだっております。どんなアホな漢字変換をしてくれるかと楽しみにしてたんですが、すんなりとカタカナに変換しちゃいましたな、サヒブ・シハブ。この人はバリトンも吹くんですが、さすがにボントロにバリサクにフレンチホルン2本では、人生あまりにも華がなさ過ぎるんぢゃないか。。。ということが懸念されたのか、ここではアルト1本に絞っているようであります。ということで、では1曲目から聴いてみましょうね。
1曲目「ロニーズ・チューン」。誰の曲だかサダカではありません。いや、調べればすぐにわかることだとは思いますが、ちょっとワケあって今は調べられる環境にはありません。が、フラーのオリジナルではないということだけはサダカではありません。日本語になってませんね。で、演奏はアディソン・ファーマーのウォーキング・ベースで幕を開けます。いいですよねぇ、ウォーキング。何かこう、サカナの王様!って感じで。(←それは魚キング。)あ、これ(←)は「うおきんぐ」と読んでくださいね。別にどうでもいいんですけどね。で、アディソン・ファーマーというのは確かアート・ファーマーの双子の兄弟で、夭折しちゃった人ではなかったかと思いますが、地味ながら堅実なプレイには定評のある人ではなかったかと思います。で、続いてはテーマの吹奏ですな。曲自体、マイナーでファンキーなムードのある佳曲なんですが、それにも増して4管による「ハモり具合」が絶妙でございますな。ま、ハモり具合が絶妙でもなければ、何もわざわざ好き好んでフレンチホルンなどという物好きな楽器を参加させる意味ははないわけなんですが、このフレンチ2人組はアンサンブルだけでなく、ソロ・パートでも大活躍をしておりまして。が、具体的にどのように大活躍していたのかと聞かれるとあまり詳しくは覚えてないので、細かい点はまた別の機会にでも書いてみようかと思っております。
で、サヒ・シバのソロがよろしいですな。いくらフレンチ界では大御所のジュリアス・ワトキンスが頑張ってみたところで、やっぱりこの楽器では地味地味感を払拭することは出来ず、それに比べてアルト配意ですなぁ。いや、アルトはいいですなぁ。オーソドックスなパーカー・スタイルが耳に心地よいです。で、ハンプトン・ホーズ。この人は黒人ではありますが、西海岸派らしい乾燥した「ぱちぱちタッチ」に特徴がありまして、が、ここではトロンボーンやフレンチホルンといった陰性の楽器に触発されたのか、かなりウェットなタッチのプレイを展開しております。ぱっと聴き、ソニー・クラークみたいな感じぃ?で、それがまたブルージーでいいんですよね。以上、記憶だけを頼りにこれだけ書ける僕はけっこう立派だと思います。
2曲目「ロック・アンド・トロール」。これはアレです。誰かのナントカというアルバムでも演奏されていた曲です。「タイトルはもちろん“六薫ロール”に懸けたもの。」という解説をライナーノートで読んだことがあったような気がするんですが、何なんでしょうね、六薫ロール?で、そっちのアルバムではわりとシンプルなアレンジで演奏されていたのではなかったかと思われますが、こっちのほうはさすがは4管編成。かなり凝ったアレンジが施されていたのではないかと思います。で、3曲目の「ア・ドリフト」なんですが、さすがに3曲目ともなるとまったく記憶にございませんので、今日はこれでおしまい♪
はい、補足編です。いや、家に帰ってこの続きをゆっくり書こうと思っていたんですが、急遽、会社の“やんぐトリオ4人組”+おっさん1名というクインテット編成でメシを食いにいくことになりまして、おかげで時間がなくなりました。よって超簡略な補足編でお茶を濁しておこうと思います。1曲目の「ロニーズ・チューン」はサルバトーレ・ジトとかいう人の作品でありました。2曲目の「ロック・アンド・トロール」はこのアルバムのプロデューサーを務めているテディ・チャールズの曲であります。ちなみにプレスティッジではプロデューサーと呼ばずにスーパーバイザーと称しているようですが、そんなことはどうでもいいです。で、このテディ・チャールズという人はヴァイブ奏者としても知られているわけですが、このアルバムでは6曲目の「ノー・クロックス」という作品において、ホーズに替わってピアノを弾いたりしちょります。で、3曲目の「ア・ドリフト」は1曲目と同じくなんたらジトという人の曲でありまして、マイナー・ムードの、なかなかよい曲でございますな。以上3曲のデキがとてもよいわけでありますが、4曲目の「ファイブ・スポット」は地味すぎて生きる希望がなくなっちゃう暗いバラード、5曲目の「リリステ」と6曲目の「ノー・クロックス」は共にテディ・チャールズの作品で、いかにもこの人らしく実験的で変な曲に仕上がっておりまして、いずれも個人的にはどうも今ひとつでありますなぁ。。。といった感じのアルバムなのでありました。おしまい。