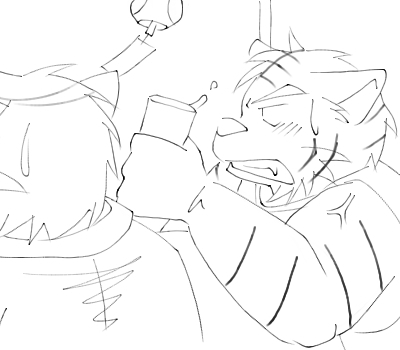野球狂の詩 前編
『おおっと! これは大きい、大きい! 入るか!? 入るか!? ・・・入ったぁー!!』
「ぃやったああああッ!!」
川本の逆転ホームランに大きく叫び、先生はガッツポーズを取った。
「やりましたね! 先生!」
「おう!」
感極まった先生が、隣の僕を抱きしめた。
汗とアルコールの匂いが鼻をつく。
「ちょ・・・せ、先生! やめてくださいよ!」
嬉しいクセに、僕は先生を押し戻した。
「おお、悪い悪い。・・・いやー、さっすが川本! イザって時ホント頼りになるがね!」
独特の方言で笑うと、先生はビールをぐっとあおった。
ぷはあっ、と酒臭い息を吐き、膝を叩いて「さすが川本!」ともう一度豪快に笑った。
ここはウチの学校の教師独身寮。
その、先生の部屋だ。
僕はいま、大好きな先生と二人っきりで、プロ野球のナイター中継を観戦していた。
応援するは、もちろん我らがドラグーンズ。
といっても、僕はそれほどファンじゃない。
先生が「超」のつくほどドラグーンズファンなので、それに合わせて応援していたら、いつの間にか好きになってしまった、という程度だ。もちろん、そんな事は先生にはナイショだけど。
先生。
ウチの学校の体育教師にして野球部顧問、柏木龍之介。(かしわぎりゅうのすけ)
もうこの名前からしてすでに、両親の代からドラグーンズファンだと容易に想像できる。まさに筋金入りなのだ。
しかしそんな先生の種族は虎人。ドラグーンズ(龍)の天敵、ティーゲルス(虎)と同じ種族というのが、気の毒といえば気の毒だった。
先生曰く、「ホントワシ、虎で生まれてきた事だけがごわくわ」だそうだ。しかも結構真剣に悩んでいるあたりが笑える。・・・いや、笑ったりしたら噛まれそうだから笑わないけど。・・・ちなみに「ごわく」とは「腹が立つ」と同義語だと僕は推測している。
特筆すべきは、やっぱりその方言だろう。
これでも標準語で喋るように努力してるんだぞ、と言ってはいたが、アレはきっとウソだ。
先生の言葉は、時々何を言っているのかわからないほど、訛りに訛りまくっている。いつだったか、エビフライのことを「エビフリャー」と言ったときには、最初冗談で言っているのかと思った。
歳は確か37歳。今年で38になるそうだ。だから当然、かなりのオジサンで、腹も出ている。なんだかオジサン臭い匂いもするんだけど、それでも僕は、この先生が大好きだった。
・・・もちろん、恋愛対象として。
僕の名前は上杉心作。(うえすぎしんさく)
17歳。華の高校二年生。
種族は狼人。毛の色は黒に近い灰色。
よく犬人と間違われるけど、それは狼人全体に言える事なので、僕の責任ではない・・・と、思う。
野球部所属。といっても補欠とレギュラーをいったりきたりの中途半端な実力だ。
当然、男。
そう。いまさらだけど、僕は男で、男に恋していた。
「良かったですね、逆転できて」
僕はグラスに入ったジュースを飲みながら、話しかけた。
テレビは今、CM中。ナイター中継はCMがやたら長い。
「ほんなもん、ドベのファルコンズなんかに負けとったら話にならんがね」
そう言う先生はとても嬉しそうだ。
嬉々として冷蔵庫を開け、缶ビールをもう一本取り出してくる。
「飲み過ぎじゃないですか?」
「まあ一本、まあ一本だけ。めでてゃーしよ」
・・・ファルコンズに負けるのは話にならないんじゃなかったんですか?
僕はそう思ったが、ツッコミはしなかった。
ドスンと腰を下ろした先生のパンツの裾から、チラリとアレが見えてしまったから。
「・・・? なにー?」
「いっ、いえ、なんでもありません」
僕は真っ赤な顔で俯いた。
今の先生の恰好は、タンクトップにトランクスだけという、非常に露出度の高い悩殺ルックだ。
そりゃまあ、自分の部屋なんだからどんな恰好でいてもいいんだけど、仮にも生徒の前なんだし、もう少し、こう・・・あ、いや、そのままの恰好の方が僕としてはもちろん嬉しいんだけど、目のやり場に困るっていうか・・・。
ああもう! これだからノンケってヤツは!
僕は思わず頭を抱えてしまう。
「?」
「あ、いえその・・・」
不思議そうな先生の視線を避け、僕は部屋を見渡した。
部屋のそこかしこに置かれたドラグーンズ応援グッズ。そのチームカラーはブルーなので、この部屋の色調で青の占める割合は非常に高い。
棚の上には、目が覚めるほど青いコアラが置いてあって、はじめて見たときはギョッとしたものだ。このコアラはドラアというドラグーンズのサブマスコットキャラ。メインはもちろん龍で、この部屋にあるものには大抵その龍が描かれている。
開け放した窓の外には、先生がいつも着ている小豆色のジャージが干してあった。
その下には蚊取り線香。
洗濯物に蚊取り線香の匂いがついてしまわないかと、他人事ながら心配になる。
「先生、エアコン付けましょうよー」
窓枠の風鈴がちりんと鳴ったが、少しも涼しくならない。
「たわけ。若ゃー頃からほんな贅沢覚わっとると、あとで往生こくでかんわ」
先生の言葉は相変わらず聞いた事のない言葉ばかりだけど、不思議と意味はわかる。
「僕は若いけど、先生はもう若くないじゃないですかー」
「おみゃあな、たいがいにしとかなあかんぞ」
「ううー」
虎人の鋭い眼光に睨み付けられ、僕は耳を寝せた。
先生はどうやらエアコンが苦手らしい。
この部屋にも付いているのだけど、動いているのはほんの1、2回しか見た事がない。
「だって暑いもんー・・・」
「しゃーにゃーにゃー」
猫の鳴き声か、はたまたマンガの擬音のような言葉を口にして(ちなみに今のは「仕方ないな」という意味)、先生は立ち上がった。
エアコン付けてくれるの? と思ったけど甘かった。
先生は、壁にかけられたドラグーンズ団扇を、「ほれ」と僕に投げてよこしただけだった。
「せめて扇風機・・・」
「なんか言やあした?」
「いいえ・・・」
僕はがっくり肩を落とすと、グラスをあおる。
空になったグラスの底で、氷がカランと音を立てた。
「暑いのがイヤなら、寮で見やあいいがね」
「談話室のテレビじゃ、ナイターなんか見せてくれませんよ」
僕は今、親元を離れ、学生寮で生活している。
その生活は「質素」の一言で、部屋にテレビを置くなんてのは考えられない贅沢だ。
寮にあるテレビは談話室の一つのみ。そしてそのチャンネルは極めて民主的に選定される。・・・早い話、多数決だ。当然バラエティ番組が圧勝し、マイノリティなナイター中継などは歯牙にもかからない。
と、いうわけで、僕は毎晩のように先生の部屋にお邪魔しているのだ。
もちろん、最初は僕だけではなかった。
野球部の連中全員で押し掛けたのが最初だ。
しかし、この地方は実はティーゲルスのホーム。当然、野球部員はほとんどがティーゲルスファンなわけで。
ティーゲルスの応援でもしようものなら、先生に噛みつかれる。・・・いや、比喩ではなしに噛みついてくるのだ。もちろん血が出るまで強く噛むわけではないが、それでも虎人の牙は鋭く、ティーゲルスファンの連中は二度とこの部屋の敷居を跨ぐ事はない。
さらにタチの悪い事に、先生は酒癖がよろしくない。
ドラグーンズが勝ったり、ホームランでも打とうものなら、先ほどのように誰彼構わず抱きつき、時にはキスしてくる事まである。
むさっくるしいオヤジに抱擁され、酒臭いキスをされるというのはノンケにとっては地獄の所行に近いらしく、その被害にあった生徒もこの部屋には二度と訪れない。
こうして、一人減り、二人減り・・・結局今ではほとんど僕一人が先生の部屋に入り浸っているというわけなのだ。
「ほーかね」
「それに、みんなティーゲルスのファンですからね」
たとえナイター中継が見れたとしても、ドラグーンズファンにとっては針のむしろだ。
「ほうか、ほうか。ホント、ワシの味方はおみゃあさんだけだがね」
大袈裟に鳴き真似する先生。そう、先生はいわば、単身アウェイに乗り込んできたドラグーンズファンなのだ。「僕もドラグーンズファンですよ」と言ったときには泣いて喜んでくれた。先生の気を引くためだけにファンになった身としては、ちょっと気が咎める思いだ。
「んじゃ、いのっちぎり応援するでな」
「はい」
ホント、もう一本ぐらいホームラン打ってくれないかな。そうすれば、もう一度抱きしめてもらえるのに。
もはやドラグーンズの勝利は決まったも同然だったが、僕はよこしまな気持ちで応援を続けた。
結局試合は6−3で、ドラグーンズの勝利に終わった。
先生は、僕にひとしきり熱い抱擁を与えると(もちろん僕は嫌がるフリだけしてみせた)、ニヤニヤ笑いながら煙草に火を付けた。こう見えて先生はよく煙草を吸う。数えていたわけではないが、今日僕が来てからでも10本は下らないだろう。
「ふー。・・・いやあ、やっぱヒーローインタビューは川本でしょー?」
「でしょうね」
僕らの意見通り、ヒーローインタビューに出てきたのは逆転ホームランを打った川本だった。
先生は美味しそうに紫煙をくゆらせると、ニヤニヤと目を細めた。
先生の大好きな選手だから、ムリもない。テレビの上には、少し色あせた川本選手のサイン色紙が大切そうに飾られている。
「龍之介君へ」と書かれているのが可笑しかった。先生の方がずっと年上なのに。
「上杉、まあこんな時間だで。はよ帰りゃあ」
「・・・そう、ですね」
本来ならこの時間に外出するのは規則違反なのだが、仮にも教師の部屋へ行くわけだし、許可は取ってある。
でも、僕が先生と二人きりでいられる時間は、ナイター中継が終わるまで。
中継が終わったらすぐ帰るという約束で、特別に許可をもらっているのだ。
「じゃ、洗い物済ませて帰ります」
僕はそう言って席を立つ。
先生は「ええて。まあ帰りゃあて」と言ってくれるけど、僕は引かない。
せめて自分が使ったグラスだけでも、と言って台所に向かう。・・・というか、わざわざジュースをグラスに注いで飲むのには、こういった時間稼ぎの意味もあるのだ。
「もう、洗い物こんなに溜めて」
「やかましいね。ほっといてちょ」
シンクの中は汚れた食器が一杯で、いかにも一人暮らしの男の部屋といった感じだ。
僕は仕方なく(といった風を装って)食器を洗い始めた。
こういうのは僕だけかもしれないが、好きな人の世話を焼くというのはなんだか嬉しい。自分で言うのもなんだけど、いいお嫁さんになれそうだ。・・・先生、もらってくれないかなあ・・・。
「・・・先生、洗い物してくれる彼女くらいいないんですか?」
僕、立候補したいんですけど・・・。
「たわけた事言やあすな。おったら部屋に生徒なんか呼ばるワケないでしょー」
もっともだ。
でも、なにもそんな言い方しなくてもいいのに。
自分から言い出したクセに、僕はヘコんだ。
ちらりと先生を盗み見ると、残ったビールをあおって、それがカラになっている事に気付いて小さく舌打ちしたところだった。
「もうダメですよ」
「わ、わかっとるがね!」
「明日一時間目体育ですよ。二日酔いになっても知りませんからね」
「しゃーから、もう飲まん言うとるでしょー!? 女房面せんといてちょ!」
その一言に、僕は少なからず傷ついた。
洗い物の手を止める。
「わかりました。・・・もう帰ります」
「・・・・・・?」
先生が不思議そうに僕を見た。
なぜ僕が怒ったのか、理解できていないようだった。・・・まあ、ノンケなんだから当然といえば当然だけど。
「・・・なんだやらひすがにゃあね。なんで?」
さすがに言葉の意味がわからず、答えようにも答えられない。
その沈黙をどう受け取ったのか、先生はフンとそっぽを向いてしまった。
いけない。
このままじゃ、気まずい雰囲気のまま帰る羽目になる。
「・・・あ、あの、先生?」
「ん?」
「・・・よかったら、明日も、来ていいですか?」
「何言うとりゃあす。明日っからはにっくきティーゲルスとの3連戦だがん。いのっちぎり応援せなあかんでしょ?」
まるで「当たり前じゃないか」とでも言いそうな先生の言葉に、僕は胸が熱くなった。
よかった。怒らせてしまったかと思ったけど、それほどでもなかったみたいだ。
「・・・はい! じゃあ先生、おやすみなさい」
「ん、おやすみ」
恋人同士だったらここでキスの一つでもしてもらえるのかな。
僕はそんな事を思ったけど、当然先生は何もしてくれなかった。
翌日水曜日。
この日は1時間目から体育というハードな日だ。
クラスのみんなは気が重そうだけど、僕としてはそうでもない。
なにしろ、朝から先生に会えるのだから。
「・・・今日は持久走なー」
顔色の悪い先生がそう言うと、みんなは口々に文句を言う。
たしかに、このクソ暑い時期に朝っぱらからマラソンなどさせられてはたまらない。
「やかましいね! 文句言うとるヤツはグラウンド5周追加! はい、よーいドン!」
みんなはブーブー不満を述べながらも仕方なく走り出した。
当然、僕もだ。
「ひでえな、柏木のやつ」
その僕の隣に並んだコースケが、先生に聞こえないように囁いた。
「ホント。朝っぱらからこれはないよね」
僕も相づちを打つ。
彼は・・・えーと・・・なんとか山浩介。僕とは一年から同じくクラスで、仲がいい。
・・・その割に名字を忘れてるけど、彼の事は教師も生徒も、みんな一様にコースケと呼ぶので問題ない。なんか、呼びにくい名字だった事だけは覚えてる。
ちょっと前まではよく遊んだけど、最近彼女が出来たらしく、付き合いが悪くなった。
「・・・でもアイツちょっと顔色悪くないか?」
「あ。気付いた? たぶん二日酔いだよ、アレ」
「あのやろ。自分が二日酔いで頭痛いからってマラソンさせやがったんだな」
コースケはそう言って毒づくが、それほど怒っているようには見えなかった。なにしろ、彼は走るのが大の得意だ。柔道部のクセに、野球部の僕よりも足が速い。
以前、何で陸上部に入らなかったのか聞いた事があるけど、笑ってごまかされた。
「ん? でも上杉、何であれが二日酔いだってわかるんだ?」
「ああ。僕、昨夜も先生の部屋に行ったから」
コースケはふうん、と頷いて「物好きだな、おまえも」と呟いた。
実は彼も一度先生の部屋に来た事がある。
酔っぱらった先生に抱きつかれ、危うくキスされそうになった生徒の一人だ。
「・・・おまえ、そのうち犯されるぞ」
冗談めかして言う。
「そんなことあるわけないよ」
そう、あるわけない。
先生は、ノンケなんだから。
「・・・あるわけ・・・ないよ」
「上杉?」
「なんでもない。・・・そう言うコースケはどうなのさ、彼女とは」
僕が言うと、コースケは目を白黒させた。
「な・・・! え? な、なんで・・・?」
「出来たんでしょ? 恋人」
コースケはしばらく黙って走っていたが、やがてポツリと白状した。
「・・・誰にも言うなよ?」
「言わないよ」
別に言ったってかまわないと思うけど、本人がそう言うなら、そんなヤボな事はしない。
でも、そうか・・・。やっぱり出来たんだ、彼女。
うらやましかった。
コースケももちろんだけど、なによりその彼女の方がうらやましい。
風呂で平常時のモノを見た事があるだけだけど、コースケのアソコはかなりでかかった。勃起したら、あれはさぞ立派なモノになるだろう。
そんなモノで相手をしてもらえる彼女が、心底うらやましかった。
「――ヘックショイ!」
・・・?
3年の校舎の方からくしゃみが聞こえたような気がしたけど、気のせいかな。
「あーあ。僕も恋人欲しいなー」
彼女、と言わないところがミソ。
そしてできれば、そのお相手は先生が・・・。
僕はグラウンドの真ん中で二日酔いと戦っている虎人を見た。
「・・・おまえの趣味はよくわからんな」
「え? なにか言った?」
「なんにも。・・・今日も行くのか? 柏木の部屋」
「あ、うん。・・・コースケも来る?」
もちろんホントは先生と二人っきりになりたいんだけど、僕は一応聞いてみた。
「まさか。馬に蹴られて死にたくねえしな」
「なんの事だよ」
「別に。・・・がんばれよ」
コースケはそう言ってペースを上げた。
徐々に遠ざかる背中を見送る。
・・・なんだよ。達観したような事言っちゃってさ。
やっぱり彼女が出来ると違うんだなあ。
僕は走りながら、大きくため息を吐いた。
夕方。
僕は晩ご飯とお風呂を速攻で済ませると、先生の部屋へ急いだ。
呼び鈴を鳴らす。
まだ帰ってきてないかとも思ったけど、先生はすぐに出てくれた。
「こんばんは」
「おう。まあ入りゃー、入りゃー」
タンクトップに小豆色のジャージという、いかにも体育教師然とした姿で迎えられ、僕は部屋に上げてもらった。
「早かったがん。まだそんな時間じゃにゃーよ?」
「ヒマだったから・・・迷惑だったら出直しますけど・・・?」
「誰もそんな事言っとらんでしょ。ワシ御飯食うとるで、ちょこっと待っとりゃーな」
「はい」
もちろんヒマなんてのはウソだ。
今日も宿題はたっぷり出されているし、みんなとバカ話でもしていればヒマを感じる事もない。
でもそれ以上に先生と一緒にいたかった。
コースケに刺激されたというのも、多少はあるかもしれない。
「あ。先生、またコンビニ弁当ですか?」
「わ、悪いかね」
別に悪くはないけど・・・。
「っていうか、何ですこれ!?」
僕はテーブルの上のモノを見て思わずそう言っていた。
「何て・・・冷やし中華に決まっとるがん」
「いえ、普通冷やし中華は白くありません」
その原因はすぐにわかった。
テーブルの上に置かれた調味料の仕業だ。
マヨネーズ。
信じられない事に、先生は冷やし中華にマヨネーズをかけて食べていた。
「おえっ・・・。なんてゲテモノ食い・・・」
「たっ、たわけか! これ、でら美味いんだに!? ちょこっと食ってみやあ!」
「いっ、イヤです! そんな気持ち悪いモノ、口に入れたくありません!」
「・・・おみゃあさん、言うようになったがね・・・」
先生はムッとして座ると、その気持ち悪い食べ物をすすった。
美味しそうに顔をほころばせる。
「なんでこの味がわからんかねー?」
・・・正直、わかりたくありません。
先生はきっと味覚が壊れている。
僕が呆れていると、先生は「それ」を食べ終わり、残ったスープを台所に流した。
「んじゃワシ、一風呂浴びてくるで、テレビでも見とりゃあ」
そう言って風呂場へ向かう。
「いいなあ、先生の部屋にはお風呂があって」
「なんで? 寮にも立派な風呂がついとるがね」
「デリカシーないなあ。部屋に欲しいんですよー」
生徒室には、お風呂どころかトイレもない。
いやそれ以前に、水道すら付いていなかった。
「たわけえ。足伸ばして入れる風呂のどこに不満があるの」
「だってみんなと一緒なんですよ? ・・・恥ずかしいじゃないですか」
寮の風呂は入浴時間が決められている。
当然、みんなと一緒に入る事になり、思春期の男子生徒にとっては死活問題だ。
「ちんぼ見られるのがそんな恥ずかしいかね?」
「そ、そういうのがデリカシーないって言うんです!」
僕が怒鳴ると、先生は豪快に笑って浴室に消えた。
もう、ホントデリカシーないんだから・・・。
「はあ」
ため息をついてテレビをつける。
といってもこの時間にロクな番組はやっていなく、僕はチャンネルを一巡させて電源を落とした。
風呂場の方から、ザバッと水音が聞こえてくる。
「・・・先生?」
聞こえなかったのか、返事はない。
僕は風呂場まで歩くと、そのドアをノックした。
「先生?」
「んー? なにー?」
「・・・トイレ借りていいですか?」
「ええよ。カギなんかかっとらんで、入ってこやあ」
「はい」
先生の言うとおり、扉にカギはかかっていなかった。僕はそっと中に入る。
先生の部屋は、風呂とトイレが共同になっていた。
といっても、トイレと浴室はガラス戸で仕切られている。
そのくもりガラスの向こうに、黄色い毛皮が湯船に使っているのがボンヤリと見えた。
・・・今、このガラス一枚隔てた向こうに、全裸の先生がいる。
当たり前の事なんだけど、そう考えると胸が苦しくなった。
・・・っと、いかんいかん。
トイレを借りに来たんだから、恰好だけでも小便をしておかないと怪しまれる。
僕はズボンのチャックを降ろすと、膀胱を絞るようにして、ちょぼちょぼと勢いのない小便をした。
その時、ザバッと水音がして、先生が湯船から上がった。
「え?」
「上杉? ワシもションベン」
「ちょ・・・せんせ・・・待っ・・・」
言い終わるより早く、ガラス戸が勢いよく開かれた。
先生の裸を目の当たりにし、僕の思考が停止する。
濡れた獣毛は肌に張り付き、その輪郭をハッキリと形取っていた。
鍛え上げられた、逞しい胸板。
それ以上に丸く突き出た腹。
そして、その下腹部。
モッサリとした茂みに埋もれた、太く逞しい男根・・・。
その雄の象徴を隠す素振りすら見せず、先生が一歩踏み出した。
威圧感からか、僕が一歩引く。
その仕草を、便器を譲ってもらったと勘違いして、先生は僕の目の前まで歩いてきた。
そしてそのまま、そのふてぶてしい男根を掴んで放尿をはじめる。
「ふー・・・」
カリの部分に少しシワがよってはいるが、その亀頭はしっかり剥けきっていて、やや黒ずんでいる。その先端から黄色い小便が勢いよく溢れ出ていた。
男根の付け根にぶら下がった金玉も、やや黒ずんでいた。ズッシリと重そうに垂れ下がっていて、ブラブラとだらしなく揺れている。
はじめて見る、先生の・・・大人のチンポ。
視線をそらす事も出来ず、僕は食い入るようにそれを凝視していた。
「・・・あんまジロジロ見んといてちょ」
恥ずかしそうに言う先生の声で我に返り、僕はハッと顔を上げた。
「あ、あの・・・その・・・」
放尿を終えた先生が、その一物をブルブル振って滴を飛ばし、水を流す。
「おみゃあさんも、はよちんぼしまやあ」
言われてはじめて、僕はチンポを出しっぱなしなのに気が付いた。
慌てて視線を下げると、僕のチンポは完全に勃起してしまっていた。
「あっ、いや、せんせ・・・これは、その・・・!」
しどろもどろになる僕に向かって先生はニカッと笑いかけ、
「若ゃーね」
と言って風呂場に戻っていく。
僕はチンポをしまう事も出来ず、ただ呆然とその後ろ姿を見送るしかできなかった。
呆然としたまま部屋に戻る。
勃起した息子はズボンの中に戻るのをかたくなに拒み、いまだ出しっぱなし。
「・・・・・・」
何が起きたのか理解できぬまま、僕はそっとそれを握りしめた。
先生・・・
そうだ。僕はたった今、何度も何度も夢想した先生の全裸を、見る事が出来たんだ。
チンポを握る手に力がこもる。
空いた手で、僕はベッドの下の引き出しを開けてみた。
そこに何があるのかは知っていた。
グラビア雑誌、すなわち、エロ本。それもなんと、無修正本だ。
無造作にしまわれたそれらの中から、一番上になっている雑誌を取り出す。
パラパラとページをめくってみると、折り目が付いていたのか、あるところでページが止まる。つまり、このページが一番使用頻度が高い、という事なのだろう。
写真の中では、大きく股を開き性器をあらわにした女性が、太く逞しい男性器をうっとりした表情で舐めていた。
・・・この写真を使って、先生はオナニーしてるんだ・・・
そう思うと、もう興奮が止まらない。
気が付くと僕は、必死になって自らを慰めていた。
写真を見る。普通、ノンケは中央の女性器に目が行くのだろうけど、僕の視線は自然とその女性が舐めている男性器に注がれてしまう。
先ほど見た先生の一物を思い出し、オーバーラップさせる。
そうだ、どこかに虎人はいないかな?
僕は思いついてページをめくった。
さすがにノンケ用の雑誌というだけあって、女性が中心だ。その中に黄色い毛皮を見つけ、僕は手を止めた。
その写真は、全裸の女性が三人の男に囲まれているという、何ともうらやましい写真だった。
そのうちの一人が虎人で、彼はその一物を女性に握らせている役だった。
「はあ・・・はあ・・・」
荒い息をしてチンポをしごく。
写真の虎人を、先生に置き換えて・・・
・・・ああ、先生が、女の人に自分を握らせている・・・
僕は切なくなって目を閉じた。
イヤだ。
こんな想像、したくない。
大好きな人が、他の人・・・それも、自分では絶対に手の届かない人とセックスしてるなんて、考えたくない。
僕は本を閉じると、そっと元の場所に戻した。
その時、引き出しの奥にある箱を見つけて愕然とする。
コンドームだ。
先生、これを使って、このベッドで、女の人と・・・
不意に涙がこぼれた。
そりゃ先生は大人なんだし、セックスだってするだろう。そんな事はわかっていたのに、こうしてその証拠を突きつけられると胸が張り裂けそうに痛んだ。
だというのに、チンポは痛いほど勃起して、快感を請求してくる。
こんな時、男の上半身と下半身が別々の脳を持っているという比喩は、見事に的を射ているなと思う。
僕は引き出しを元に戻すと、立ち上がった。
浴室からは水音に混じって先生の鼻歌が聞こえる。ドラグーンズの応援歌というのが、いかにも先生らしい。
僕は扉に耳を付けると、その歌声をオカズに自慰をした。
目を閉じ、先生の裸を思い出す。
筋肉の盛り上がった胸。
その先端にぷっくりふくらむピンクの乳首。
脂肪の付いた丸い腹。
硬そうな尻たぶに垂れ下がる長い尻尾。
ズッシリと重そうな金玉。
そして。
太短く、ふてぶてしい先生自身・・・。
「ああ・・・先生・・・はぁ、ん・・・先生・・・っ」
快感の波が押し寄せた。
あまり時間をかけるわけにも行かず、僕はそれを受け入れる。
「う・・・んん・・・あっ、い、イク・・・ッ」
そして僕は射精した。
亀頭を包み込むように持ったティッシュの中に、ぴゅっぴゅっと精液を飛ばす。
ひとしきり痙攣した後、僕は震える体を扉に預けた。
「せ、せんせぇ・・・」
扉の外でこんな行為が行われているとは夢にも思っていない先生は、相変わらず呑気に鼻歌を歌い続けていた。
僕はオナニーの後始末を済ませ(といってもティッシュを捨てるだけだが)、何食わぬ顔でテレビを付けた。
しばらくニュースを見ていると先生が風呂から上がり、頭を拭きながらやって来た。
「まだ始まっとらん?」
パンツ一丁で先生は腰を下ろす。
「はい、まだです。・・・先生、服はちゃんと着て下さいね?」
「わ、わかっとるがね」
まったくもう。
せっかく興奮が治まったというのに、そんな恰好でいられたらまた勃起しちゃうよ。
「・・・ホント、これだからノンケって・・・」
「んー? 何か言うた?」
タンクトップを窮屈そうに着ながら、先生。
「なにも」
「ふーん」
気のない返事をすると、先生は冷蔵庫の中からビールと枝豆を取りだしてきて、再び腰を下ろした。
「ほんじゃ、今日もドラグーンズの勝利を祈って」
「乾杯」
缶ビールとグラスを合わせる。
だから音なんてしなかったけど、代わりに風鈴がちりん、鳴った。
「・・・ぷはあ!」
ビールをあおり、美味しそうに息を吐く先生。
「・・・いつもながら、美味しそうに飲みますね」
「だってでら美味いもん。やっぱ風呂上がりのビールは最高だわ!」
口元の泡を拭って先生は言う。
「ふーん・・・」
「ダメダメ。おみゃあさんは大人になるまでガマンせなあかん」
「わかってますよ。・・・いいなあ、大人は」
「ワシに言わせりゃ、若ゃーおみゃあさんらの方がけなるいけどね」
そんなモンだろうか。(ちなみに「けなるい」はうらやましい、の意)
「学生なんて何も出来ないじゃないですか。お小遣いは少ないし、煙草も吸えないし、お酒も飲めないし・・・」
早くも酔っぱらったのか、先生は僕の肩に手を回して囁く。
「・・・エロ本も買えーせんしな」
「なっ・・・ぼ、僕はそんなもの欲しくありませんよっ」
「ほうかね? さっきちんぼ勃てとらしたのはどこのどいつだった?」
いやらしく笑う先生の言葉に、僕の顔がカッと熱くなった。
「だ、だから、あ、あれは・・・っ!」
「わかっとるて。誰にも言やーせんから安心しやあ」
「もうっ!」
僕は先生の腕を振り解いてそっぽを向いた。
あのままの体勢でいられたら、また勃起してしまう。・・・というより、僕はすでに半勃ち状態だった。先生に気付かれたら、またからかわれてしまう。
「ほれ、中継はじまったで」
先生はいつの間にか火を付けたタバコでテレビを指した。
・・・ヤバイなあ。
こんな状態で先生に抱きつかれたら、僕は自分を抑えきれないかもしれない。
しかし、その心配は杞憂だった。
なぜならこの日、ドラグーンズは一本のホームランも出さず、負けてしまったのだから。
5−0の惨憺たる試合結果。
さっきまでの上機嫌はどこへやら。先生はあからさまな不機嫌顔でビールをあおった。
「・・・惨敗、でしたね」
ティーゲルスのヒーローインタビューを見つつ、僕は言った。
「惨敗じゃにゃあ! 惜敗だがね!」
そうかなあ。
僕が見た限りじゃ、今日のドラグーンズにいいところは何もなかったように思えるんだけど・・・。
先生もそれに気付いているのか、ビールの空き缶をクシャッと握りつぶし、叩き付けるようにテーブルに置いた。
「ああもう! ごわくでかんわ! ワシまあ寝る!」
敵のインタビューなど見たくないといった感じでテレビを消すと、先生は飛び乗るようにベッドに横たわった。
ベッドのスプリングが軋んで悲鳴を上げる。
「おみゃあさんも、早よ帰りゃあ」
「はーい」
そう言いながらも、僕は台所に立つ。
シンクの中には昨日と同じく、いや、昨日よりもたくさんの食器が放置されていた。
「もう、仕方ないなあ。これ洗ってから帰ります」
「・・・勝手にしやあ」
僕の相手をする気にもならないのか、先生はベッドに寝ころんだままおざなりに答えた。
数が数なだけあって、なかなかに苦戦してようやく全ての食器を洗い終えると、僕はタオルで手を拭きながら部屋に戻った。
「じゃあ先生、僕もう帰り・・・」
その言葉が止まる。
先生は、だらしなくベッドに横たわってイビキをかいていた。
両腕を枕にし、わきの下を見せて眠る先生。そのタンクトップが、ヘソの上までたくし上げられている。
それだけならまだしも。
先生の股間は、明らかに膨らんでいた。
「せ、先生・・・?」
小さな声で名を呼ぶが、帰ってくるのはイビキばかり。
僕はそっとベッドの脇に立って、先生の寝顔を見つめた。
ゴクリと喉が鳴る。
頭の中が真っ白に染まっていった。
「先生?」
ちょっと大きめの声で呼んでみる。
が、返事はない。
ダメだと思いつつも、僕はリビドーを抑える事が出来なかった。
床に膝を付き、先生の身体へ鼻を近づけると、酒臭い体臭が鼻孔をくすぐった。
先生の様子をうかがいながら、その大きなお腹にそっと触れてみる。
柔らかい感触が手のひらに伝わり、興奮が加速する。
ダメだ、これ以上は・・・。
頭ではそう理解しているのに、手が止まらない。
なだらかな丘を、徐々に降りていく手のひら。
そしてそれは、とうとう先生の股間に到達してしまった。
包み込むように、そっと握ってみる。
その、芯のある柔らかさが、僕の理性を打ち砕いた。
どくん、どくん、と心臓が早鐘のように鳴り響き、異様にうるさい。
「せん・・・せぇ・・・」
気が付くと呼吸も荒い。
僕のチンポはもうとっくに勃起しきっていたが、今はそんなものに触れている余裕はない。
・・・先生も、僕の勃起を見たんだから、僕だって見てもいいよね・・・?
僕はそう訊ねるように先生の寝顔を確認すると、パンツの社会の窓に手を伸ばした。
両手で生地の左右を掴み、引っ張る。
開かれた社会の窓から、半勃ちの先生が顔をのぞかせた。
「・・・ああ・・・せんせぇ・・・」
窮屈なパンツの中から解放され、先生はそのお礼とばかりに僕の目の前で成長してくれた。
ぴくん、ぴくんと跳ね上がりながら、その都度大きさを増していく。
すごい。
なんて大きさだ・・・。
長さはもとより、なにしろ太い。凶悪とも呼べるサイズだ。
こんな大きなモノで相手をしてもらえたら、どんなに幸せだろう。
でも、この巨根を相手に出来るのは女性だけなのだ。
果たしてこのチンポは一体、今まで何人の女性を貫いてきたのだろうか。
そう考えると胸が苦しくなる。
でも、今だけは。
この一瞬だけでも。
僕は先生を独り占めしたかった。
「・・・好きです・・・先生・・・」
僕はそっと先生自身に口づけした。
血管の脈動が唇に伝わる。
僕は舌を出し、先生の裏筋を舐め上げると、その大きな亀頭を口に含む。
この大きさだと、亀頭をくわえるだけで一杯一杯だ。
僕はしばらくそのまま、先生を味わっていた。
涎が溢れ、口の隙間から垂れて竿を伝わっていくのがわかる。
涎を飲み込み、亀頭を舌で舐め上げると、先生が「うっ」と呻いた。
「!!」
慌てて吐き出す。
ほとんど同時に先生が寝返りを打ち、僕に背を向けてしまった。
・・・危なかった。
吐き出すのがもう一瞬遅れていたら、先生の寝返りに間に合わず、目を覚まされてしまったかもしれない。
もしあんな状態で先生が目を覚ましたら、と考えると、背筋に冷たいものが流れた。
さっきとは状況が違う。「若いな」の一言で済まされる行為ではないのだ。
「・・・ごめんなさい、先生」
謝って、僕は先生の身体に毛布を掛けた。
「あの、僕もう帰りますね」
出来るだけ平静を装って、大きな声で言う。
先生はわかっているのかいないのか、んー、と返事をした。
胸をなで下ろし、僕は先生の部屋を後にする。
ドアを閉める瞬間、先生の寝言が聞こえたような気がした。
「・・・なに考えとりゃあす・・・たわけ・・・」
つづく。