
|
ぱんさのマイナー植物園
テマリカタヒバ
|
|
このページは、アーガイブに収録しているものです。 ぱんさは、テマリカタヒバの栽培に完全敗北してしまいました(つまり枯らしてしまいました。)。 この植物は、夏以外は比較的調子が良いのですが、夏の暑さに極めて弱いようで、夏が訪れるたびに葉枯れが発生し、2年目には枯死してしまいました。 自生地は、メキシコの高地1,000m〜1,600mの峡谷等に自生しており、そこは1年を通じて温度差のあまりない(10〜20℃)、冷涼な地域のため、成長させるには夏でも30℃を超えない冷涼な気候であることが必要なようです。日本のイワヒバとは、難易度に天地の差があります。 成長させずにたまに復活させるようなドライフラワーもどきの栽培方法ならもっと永く持たせることが可能ですが、自生地のように元気いっぱい成長させることができなければ、栽培するだけの意味はありません。 |
| 更新情報 |
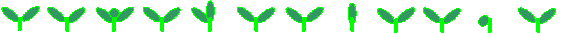
まずは、以下をご覧ください。
 カラカラに干からびた枯れ草のボール??鳥の巣?
水を与えると! 
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
テマリカタヒバとは
この植物は、場合によっては、Selaginella pilifera セラギネラ・フィリフェラと呼ばれることもありますが、これが誤用であるのか、別名であるのかはっきりしません。
カラカラの乾季が訪れると、乾燥し茶色く枯れたようになり丸くなりますが、雨季には、葉を広げ劇的に緑色になります。その生態から、死んでも甦る植物とされ「復活草」とも呼ばれます。(実際は、カラカラに乾燥していても、本当に死んでいるのではない。) 日本にも、近縁のイワヒバという植物があり、テマリカタヒバよりも小型ですが、同じような性質を持っています。ただし、これは、テマリカタヒバほど極端な気候の土地に自生するわけではありません。
まず、この植物は雨季と乾季がはっきりした岩山に自生します。サハラのような砂ばかりの砂漠に自生するわけではありません。岩山で転がれば、尖った岩に当りまくり、10mもいかないうちに、植物はバラバラになってしまうでしょう。カラカラに乾いても根はしっかり大地に下ろし、人間が「出荷」のためにワザと切らなければ生えている地面から離れません。また、植物にしても、乾季には次の雨季を待てばいいので、あえてコロコロと転がって移動しなければならないという必然性がまったくありません。 いかにも転がりそうな丸さや、西部劇などに出てくる、転がる玉状の枯れ枝(タンブル・ウィード 、Salsola collina)とイメージがごっちゃになってそんな空想が生まれたのかもしれません。
なぜ、テマリカタヒバは、カラカラになっても、再び復活するのか? テマリカタヒバは、いわゆる、ドライフラワー的な装飾品という扱いで、日本に輸入されてきます。 私としては、インテリアや装飾品ではなく、植物として育てることを目標としています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
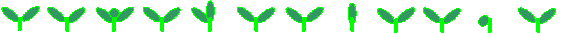
先ず、カラカラに枯れたテマリカタヒバの全体を濡らし、下半分を水につけておきます。 約12時間で開き、生きていれば緑色を復活させます。 なお、完全に枯れている場合は、繊維が水を吸って(自動的に)葉は開きますが、緑色には戻りません。期待して待っていても腐敗が始まります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メキシコの気候 どうやって育てるかを検討するために、メキシコの気候を調べ、日本の気候と比較しました。
日本の典型的な気候は、低温で雨の少ない冬と高温で雨の多い夏があり、その間に春と冬があります。つまり、四季があるということです。
メキシコは一年を通して冷涼、温暖で、四季というものがありませんが、乾季と雨季がはっきりしています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「予想される」栽培方法
自生地は、メキシコ産のサボテン(例えば、Echinocactus ingens 「巌」)とほぼ同じなので、同等の環境で栽培すればいいと考えてきました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
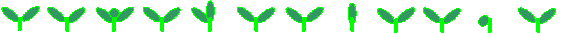
枯死させてしまわなければ、段階的に記載を予定。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
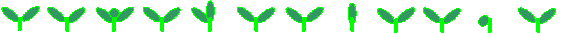



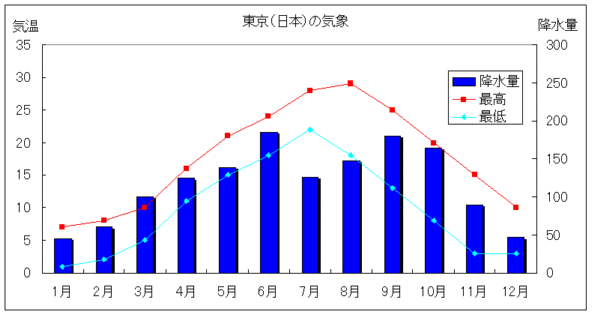
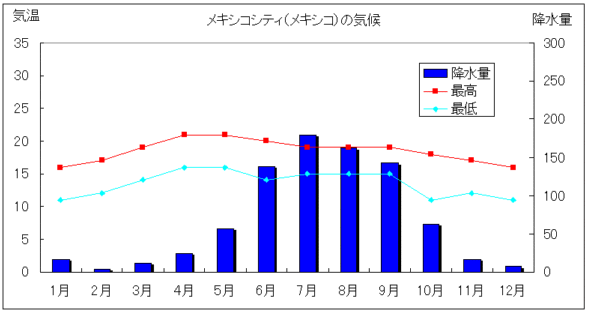




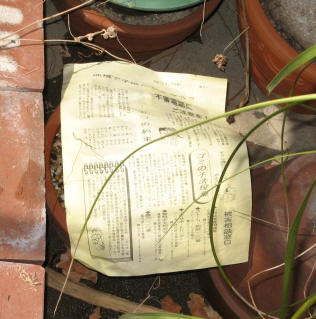







 『ぱんさのマイナー植物園』に戻る
『ぱんさのマイナー植物園』に戻る