|
このページはエキサイトブログで2004年3月に掲載した書評・映画評覧で構成されています。
新規の書評は
→ここ、シーサーブログの「新・読書記録゛(どくしょきろぐ)」
でお楽しみいただけます。
ゴシカ
 ホラー好きの私としては、これを見ないわけにはいかないなあ、ということで見てきましたよ。 ホラー好きの私としては、これを見ないわけにはいかないなあ、ということで見てきましたよ。
さて、ホラーのカテゴリにも色々ありますが、この作品は、幽霊(ゴースト)もので前半から引っ張っていきます。
このあたりの描写は、「リング」とか「呪怨」とかの日本ホラーの影響が濃厚。
よく勉強していますね、というところ。存分に震えることができます。
また、精神科医である自分が精神を病んでいるのでは、という内的な恐怖もなかなか見せる。
が、後半、映画は急速に「サイコ」ものになっていく。
これがまた怖い。
見終わった後、本当に恐ろしいのは「幽霊」ではなく「人間」の方であるということに気づく。アメリカの田舎の方では、こんなこと本当にありそうだ。
ホラーで始まり、サスペンスで終わる。こういうのもありでしょう。
意欲的な作品だ。
ゴシカ 特別版 〈2枚組〉←アマゾンへGo!
↑このページのトップへ
シリーズ物語について考えた
小説にせよマンガにせよ映画にせよゲームにせよ、ファンのはまりやすい「シリーズ物語」というフィクションの形式がある。
作者にしてみれば、登場人物が走り出してしまえば、もう何かに憑かれたように書いていける場合もある。
大まかには次の二つの要素で成り立つと思われる。
●舞台となる世界観を共通とする物語
テレビゲームのRPGや、ファンタジー小説でおなじみの形式だ。最近では「十二国記」(小野不由美)が読み応えがあってよかったな。
考えてみれば、RPGをプレイするということは、プレイヤーがその世界で、一定の約束事の中で自分の物語を作ることである。プレイヤーの数だけ物語があるわけだ。
●舞台は違えど登場人物の物語を固定してしまう物語
極端な表現だが、これの代表は、007シリーズだろうか。
「世界征服をたくらむ悪の組織」に「潜入・捜査」して「一度は捕らえられ」、「美しい敵側の女を籠絡」して「脱出」、「戦力を整えて」「反撃」という構図は見事なまでに守られている。映画「私を愛したスパイ」が、過去のシリーズの中で最も人気のあったシーンを集めてきて脚本を上げたというエピソードが、その証拠といえようか。
また、寅さんシリーズもそうだよね。
現実に市場に出回っているシリーズ物は、以上の二要素の組み合わせである。
真にオリジナリティーのあるシリーズを作りたければ、上記の二要素を根底から覆すような話を考えればいいわけだが、でもそれが面白いかどうかは保証の限りではない。
いわゆる、シリーズのファンにとっての「気持ちよさ」は失われてしまいそうだからだ。
↑このページのトップへ
「霊感・霊能の心理学」(中村希明)朝日文庫 93年
 ホラー小説、ホラー映画マニアである私は、心霊現象や怪奇現象も嫌いではない。ただ、さすがにすべてを本気で怖がり、信じるほど若くはなくなった。その一因となったのが、本書をはじめとする心理学や精神病理学の本を読んだことである。 ホラー小説、ホラー映画マニアである私は、心霊現象や怪奇現象も嫌いではない。ただ、さすがにすべてを本気で怖がり、信じるほど若くはなくなった。その一因となったのが、本書をはじめとする心理学や精神病理学の本を読んだことである。
人間は、どんなに科学が発展しても、それに応じてさらに未知なもの神秘的なことを求めてやまないのだと思う。
かつて、神や悪魔を信じていた人々は、科学が発展するにつれて、今度は宇宙人や超能力や未確認生物など、科学的(に見える)な神秘を求めていく。以前読んだ本で、神秘事件発生のパーセンテージは不変である、というのを知った。
18世紀以前、悪魔や幽霊や狐や狸が原因という目撃事件が主である。が20世紀になると、その手の事件は激減して、変わりにUFOなどが登場する。つまり、人間は必ず、一定のパーセンテージで、そういうものを見る(見たような気になる)ものなのである。まったく身も蓋もありませんね(笑)。
本書の中でも白眉なのは「名作の精神病理学」で、四谷怪談を分析するところ。伊右衛門の幻覚はまさに「錯視」という症状そのもので、そんな知識など無かったであろうに、それを演出として用いた南北の洞察力はすごい。
といった具合に、現実の心霊や霊感を大槻教授よりずっとスマートに切っていく。そのうちに、そういった現象を頻繁に感じる現代社会の病理的な部分も見えてくる、という本である。
壺とか買っちゃいそうな人は是非読んでおくといいよ。
霊感・霊能の心理学朝日文庫←アマゾンへGO!
↑このページのトップへ
「朝、上海に立ちつくす 小説東亜同文書院」(大城立裕)中公文庫
 みなさんは東亜同文書院という日本の大学を知っているだろうか。 みなさんは東亜同文書院という日本の大学を知っているだろうか。
1901年(明治34年)東亜同文会(会長近衞篤麿貴族院議長)によって中国の上海に創立された。日中提携の人材養成を目的とし、戦前海外に設けられた日本の高等教育機関としては、最も古い歴史を持つ。中国・アジア重視の国際人を養成し、ここから日中関係に貢献する多くの人材が育った。
特に学生達が授業の一環として行った「調査大旅行」は中国各地を調査する学術旅行で、この大学の大きな特徴として伝えられている。
が、悲しいかな建学の理想とは裏腹に、大戦中はこの旅行すら軍の調査に利用され、学生達も通訳として兵役に赴いたのである。
この物語の主人公は、日本人ではあるが、沖縄出身(作者の分身である)であり、支配側の日本と支配される側の中国との間に位置する。
日中両国の学生たちのとまどいやいらだちやあせりを通して、この悲しい運命の大学とその果たした役割を描いている。
実は、私の母校の愛知大学は、終戦でこの同文書院が閉鎖された時の学生と教授達によって、豊橋に建学された、いわば同文書院の残党のような立場である。そんなこともあってこの本を手にしたのであった。
戦争と日本による中国支配に利用された国策大学という汚名を着せられていた同文書院の真の姿を伝えたい、そんな作者の声が聞こえるようだ。青春小説としても優れている。
※愛知大学の現代中国学部では、3年次の3週間、学生自身が中国を訪れ、中国社会の実情を多面的に調査。その結果を、中国主要大学の学生との日中学生シンポジウムで発表、ディスカッションしている。これは同文書院の「調査大旅行」に相当するのだ。
朝、上海に立ちつくす―小説...中公文庫←アマゾンへGO!
→東亜同文書院大学記念センター
→愛知大学
↑このページのトップへ
「OUT」(桐野 夏生)講談社文庫
 先日、映画版を見たので読み返した。で、結論として、映画版は見なくてよい(笑)。また映画だけ見た人は、必ず原作を読んで欲しい。映画だけで判断しては、桐野女史が気の毒だから。 先日、映画版を見たので読み返した。で、結論として、映画版は見なくてよい(笑)。また映画だけ見た人は、必ず原作を読んで欲しい。映画だけで判断しては、桐野女史が気の毒だから。
パートタイマーの主婦雅子はパート仲間が殺してしまった暴力亭主の死体を処理するはめになる。それをきっかけに、彼女たちの平穏な日常が、崩れていく。
それでも、その「平穏な日常」を嫌悪していた主人公は、その中でたくましさをましていくのである。すごい。作者が女性であるからこそ紬出せた物語であろう。
読後感は重い、しかし、カタルシスがある。雅子の強さ、「男まさり」のようなかっこよさはなく、ちゃんと「女性の強さ」ならではのかっこよさである。俺と同様、この主人公の強さに喝采を送った読者も多いのではないか。
昔、「単調で貧しい日常に倦み疲れた独身労働者(つまりは俺のような)」のカタルシスは「大藪春彦」の小説だった。暴力を背景にのさばる連中を、それを上回る暴力で倒していく大藪小説。
「OUT」を読んで、これは「平穏な日常に倦み疲れた女性」のための小説なのだと思った。桐野夏生は女達のための大藪春彦になったのである(←少し暴論・笑)。
OUT 上 講談社文庫 き 32-3←アマゾンへGO!
↑このページのトップへ
「人身御供論―通過儀礼としての殺人」(大塚 英志)角川文庫
 村を救った猿神のもとへ輿入れした少女が、夫を殺害して村に戻ってくるという昔話「猿聟入」。そこで語られた供犠と異類殺害の物語は、その後のマンガ、小説、映画などにも繰り返し現れてくるいわゆる物語のフォーマットである。 村を救った猿神のもとへ輿入れした少女が、夫を殺害して村に戻ってくるという昔話「猿聟入」。そこで語られた供犠と異類殺害の物語は、その後のマンガ、小説、映画などにも繰り返し現れてくるいわゆる物語のフォーマットである。
過去の民話と現代のサブカルチャーを通庭するものは「通過儀礼」である。通過儀礼とは、ムラなどの閉鎖された秩序の中で、「子供」という神の領域に近い存在を「大人」という社会の一員として内部に取り込むことである。儀礼の後は、青年小屋のような場所にこもった後、社会の一員として仕事が与えられる。近代となってムラ社会が崩壊した後は、ムラを出て「都市」へ行くということが通過儀礼になっていく。しかし、全国がほとんど「都市」となった現在、子供達は「通過儀礼」を失っているのだ。今や、「通過儀礼」は与えられることなく、個人が自力で「成熟」することで果たすしかない。ある意味、なんと厳しい時代ではないか。
社会が自由になり、自分のすべての選択を自分の責任で果たさなければならないときに、人がその自由の重み前でおののくように(→実存主義やね)、若者は、「成熟」することにおののいている。
作者は、せめて、ビルドゥングス・ロマンが、この通過儀礼の間の「移行対象」(いわゆる「ライナスの毛布」や「熊のぬいぐるみ」のように成長の過程で母とかの代替として機能し、成長後は不要となって「捨てられる=殺される」人身御供)となりうるのではないかと考える。そして積極的にそのようなロマンを提供しようという決意表明になっている。
「タッチ」「ホットロード」「めぞん一刻」から「鉄腕アトム」まで、、「民俗学者」大塚英志が分析するところが面白い。眼からウロコである。創作に携わる人間は必読といえる。
私も以前、「通過儀礼」もののホラー作品を書いたことがある。↓
「盂蘭盆会・・・参り(うらぼんえふせじまいり)」
これは、32歳の時、長女が生まれたばかりの時に見たグロテスクな夢がモチーフになって生まれた小説だ。何故そんな夢を見たかが不思議で、文芸仲間の友人が「作品化することでわかるかもしれない」と言ったことをきっかけに書き始めたものである。
書くことによって、はじめて父(確固たる社会の一員)になるということに、本能的におびえていた自分の心と直面することができ、その心と決着をつけることができた作品である。「小説を書く」ということが、俺にとっての一つの「通過儀礼」だったのだ。
同じことは俺の他の作品にもあてはまる。その当たりは、また項を改めて書いてみたい。
人身御供論―通過儀礼として...角川文庫←アマゾンへGO!
↑このページのトップへ
「千里眼 マジシャンの少女」(松岡圭祐)小学館
 千里眼シリーズの七作目であり、マジシャンシリーズを取り込むような形で展開する。 千里眼シリーズの七作目であり、マジシャンシリーズを取り込むような形で展開する。
お台場に作られた一大カジノの試験運用会場が、島ごとテロリストに占拠される。作者お得意の大風呂敷をはじめとして、突っ込みどころの多い作品だ。でもやっぱり一番の突っ込みどころは主人公のスーパーレディ岬美由紀だろう。
防衛大学出身、航空自衛隊幹部候補生からF15Jイーグル戦闘機パイロットを経て、現在は「千里眼」の異名を取る臨床心理士(カウンセラー)って書いているだけで苦笑い。
でも、いったん読み始めるや、とにかくやめられない。
極めて辛口の俺が、松岡圭祐の本は、全部「自分で購入」して読んでいるのが何よりの証拠だ。
このシリーズは、昔夢中になった、「ウルフガイ」とか「ゾンビーハンター」とか、「魔獣狩り」といったシリーズを彷彿とさせる。ページを繰らせる力とでも言えばいいか。
また格闘オタクの俺には主人公・美由紀が中国拳法の達人という設定もうれしい。でも文章で表現されたアクションはおそらく素人にはちんぷんかんぷんでしょう。旋風脚とか騰空擺蓮とか書いても伝わるのは雰囲気だけだ(伝わる俺の方がある意味おかしい・笑)。
で、岬美由紀がしばしば披露する得意技・旋風脚(シュエンフォンジアオ)というのがこの写真。筆者(俺)自らがモデルとなりました(撮影・息子)、憧れて練習しましたよ。ビデオを手本に一人練習(←ホーリーランドかよ、俺)↓
回り切れていないとか、低い、とか突っ込みどころの多い写真ですが、46歳のハゲオヤジがやってることですからお許し下さい。

千里眼/マジシャンの少女小学館文庫←アマゾンへGO!
↑このページのトップへ
「シン・レッド・ライン」
 俺的には、戦争映画の傑作である。 俺的には、戦争映画の傑作である。
太平洋戦争の激戦地ガダルカナルを舞台にしている。隊をたびたび離脱する二等兵ウィット(ジム・カヴィーゼル)。彼やウェルシュ曹長(ショーン・ペン)が所属するC中隊を率いるスタロス大尉は、部下たちの命を守ることに心をくだく人物。
日本軍がたてこもる丘を出世のために占領したいトール中佐(ニック・ノルティ)に対し、スタロス大尉は無謀な前進を拒絶。その頃、隊は日本兵のトーチカを突き止めることに成功。丘攻略を目指して激しい攻撃を開始する…。といった内容のストーリーはある。が、この映画の描くのは戦闘でも戦略でもない。「戦う、殺す、殺される」という人間のいわば原罪に直面した兵卒たちが、ある者は心を病み、ある者は感覚を麻痺させてそれに慣れていくところを描いている。
脱走常習者のウィットは冒頭、平和で美しいポリネシアの島に隠れている。が物語の中盤、彼が再び訪れたそのパラダイスは、争いで人々が互いに背を向け合っていた。つまり、「互いに争う」ということは人間の逃れられない「業」なのである。パラダイスなどないのだ。
主人公と思われたウィットは終盤自ら選んだかのように戦死する。そして、心を病むほど弱くなく、心を麻痺させてしまうほど絶望しきれないウェルシュこそが、この映画の主役であることがわかる(わかる観客は少ないかもしれないけど)。
彼は、この人間の「業」に絶望して死のうとはしない。心を麻痺させ眼をつぶろうともしない。その痛みを「痛み」として「しっかり見つめよう」とする。少なくとも、それが「痛み」として感じられるうちは人間に絶望しないぞ、という映画なのである。
映画の中には、この「痛み」を感じなくなっている登場人物も出てくるから、そのテーマは明白でしょう。こんな作品を作って公開するからアメリカは映画大国なのである。
ということで、同じ時期に公開された「プライベート・ライアン」と比較して、「つまらない」なんてほざいた連中は、自分の馬鹿さ加減を宣伝したようなもんですな。
「プライベート・ライアン」は人間の「業」になど思いを馳せない「七人の侍(欧州戦線版)」なのだから、そもそも比較してはいけない作品なのだ。
この作品のように内省的で哲学的な戦争映画といえば、シドニー・ポラックの「大反撃」(これも傑作)ぐらいである。「地獄の黙示録」も比較されやすいが、「黙示録」の方は、「これはただの戦争映画ではありません!」と作品全体が大声で喧伝しているようなところがあり、大人げないなと感じてしまう。
また日本軍の描写が正確で、偏見が一切無いことも特筆できる。少なくとも一「兵卒」達は敵味方の区別無く、「被害者」なのだということがひしひしと伝わってくる。
シン・レッド・ラインTHIN
RED LINE←アマゾンへGO!
↑このページのトップへ
|
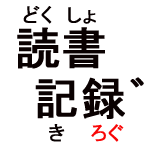



 ホラー好きの私としては、これを見ないわけにはいかないなあ、ということで見てきましたよ。
ホラー好きの私としては、これを見ないわけにはいかないなあ、ということで見てきましたよ。 ホラー小説、ホラー映画マニアである私は、心霊現象や怪奇現象も嫌いではない。ただ、さすがにすべてを本気で怖がり、信じるほど若くはなくなった。その一因となったのが、本書をはじめとする心理学や精神病理学の本を読んだことである。
ホラー小説、ホラー映画マニアである私は、心霊現象や怪奇現象も嫌いではない。ただ、さすがにすべてを本気で怖がり、信じるほど若くはなくなった。その一因となったのが、本書をはじめとする心理学や精神病理学の本を読んだことである。 みなさんは東亜同文書院という日本の大学を知っているだろうか。
みなさんは東亜同文書院という日本の大学を知っているだろうか。 先日、映画版を見たので読み返した。で、結論として、映画版は見なくてよい(笑)。また映画だけ見た人は、必ず原作を読んで欲しい。映画だけで判断しては、桐野女史が気の毒だから。
先日、映画版を見たので読み返した。で、結論として、映画版は見なくてよい(笑)。また映画だけ見た人は、必ず原作を読んで欲しい。映画だけで判断しては、桐野女史が気の毒だから。 村を救った猿神のもとへ輿入れした少女が、夫を殺害して村に戻ってくるという昔話「猿聟入」。そこで語られた供犠と異類殺害の物語は、その後のマンガ、小説、映画などにも繰り返し現れてくるいわゆる物語のフォーマットである。
村を救った猿神のもとへ輿入れした少女が、夫を殺害して村に戻ってくるという昔話「猿聟入」。そこで語られた供犠と異類殺害の物語は、その後のマンガ、小説、映画などにも繰り返し現れてくるいわゆる物語のフォーマットである。 千里眼シリーズの七作目であり、マジシャンシリーズを取り込むような形で展開する。
千里眼シリーズの七作目であり、マジシャンシリーズを取り込むような形で展開する。
 俺的には、戦争映画の傑作である。
俺的には、戦争映画の傑作である。